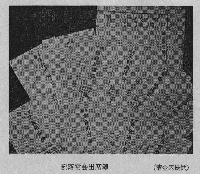
<< part1へ [part2]
==第二節 銃後の活動==
一、在郷軍人分会
明治四十三年に大日本帝国在郷軍人会が創設されたのを機会に、わが村ではそれまであった軍人会を改組して、軍隊を経験した人達によって富奥村在郷軍人分会と改めた。明治四十四年の創立である。ただちに会旗を樹立して、会員の修養と鍛錬はもちろん訓練や村の事業などへ積極的協力をし、徴兵で入退営する若者達の歓送迎から、出身者の軍隊慰問、戦死者の慰霊など目ざましい活躍をした。とくに戦死者の霊を合同でまつる忠魂碑を、村の中央である現在地に建てたのも軍人分会であった。こうして銃後の第一線に立って活躍し、留守家族などの援助なども惜しみなくしながら、ほとんどの男子が出征したので、その頃の活躍は並大抵でなかった。が、終戦と同時に役場の前で伝統を誇った分会旗や関係書煩を焼却して、「GHQ」の追及を逃がれたのである。
大正五年の本村の自治一覧表によると、在郷軍人数一一六名、現役軍人陸軍一一名、海軍六名となっている。
歴代在郷軍人分会長(伊藤好麿調べ)
1中野昌次(清金) 2仏田弘俊(上林) 3杉野三郎(下林) 4沢村庄松(下林) 5東週二 (清金) 6伊藤好麿(下林) 7谷好信(下新庄) 8西本博義(上林) 9吉岡治作(下林) 10山田一郎(中林) 11高納友春(位川) (以後、敗戦によって消滅)
明治四十五年七月三十日に明治天皇が崩御された。その葬儀に第七連隊で第一中隊で序列一番の清金の中野昌次氏が第七連隊代表として隊旗をもって参列したことが残っている。また、富奥村から近衛師団に入営した人は次の人達である。近衛師団とは天皇陛下、即ち東京の宮城を守る軍隊である。ここに入隊することを当時は名誉としていた。
仏田弘俊(上林) 中島一孝(太平寺) 安田庄一(中林) 中村一信(粟田) 宮岸伝二(三納) 杉本喜佐男(粟田)
大正四年御即位諸式日時記(大正天皇即位式)
(清金区書類の中より)
十一月六日 東京発
十一月八日 京都着
十一月十月 御即位式
〃 三時三十分 総理大臣大隈重信万歳三唱奉祝
十一月十一日、十二日 御神楽ノ御儀
十四日 大嘗祭
十六日、十七日 大賜宴会
十九日から廿五日まで 神宮及各御陵御親閲
十二月二日 陸軍大観兵式(在郷軍人会参列)
富奥在郷軍人分会参列者
山本茂堆 中山喜一郎
十二月四日 観艦式
十二月六日 在郷軍人会大会 (勅語下賜)
十月十八日 大禮諸員賜饌
二、銃後の活動
大政翼賛会が結成されて、日本はあげて戦時体制一色となり、わが村の中島栄治氏は村沢義二郎氏らとともに翼賛議員に推せんされ、活躍した。
富奥村銃後対策実行協議会々則
一、賛助会員 金一円以上拠出シタルモノ
但シ一円以下ハ寄附金トシテ申受ク
第七、八附則(省略)
右のような会則が出てきたが、何年何月と書いてないのが惜しい気がする。とにかく、銃後の堅い守りが出征兵士の士気に与える影響が大であるということと、銃後の活躍が目ざましければ当局から賞賛された。それよりも銃後の活動が国を守ることであり、天皇陛下のためという当時の絶対的な忠君愛国の心から、やむにやまれぬ国民の行動であった。
三、出征兵の歓送迎
戦争が起こると必ず赤紙動員という召集令状が役場から兵役にある本人に届く。それもたいてい夜おそく知らされるのである。現役の軍人はもちろん戦争に参加するのだが、除隊して村の在郷軍人に籍のある人は必ず召集されるのである。
明治から大正、昭和へと、この戦争参加によってどれだけの村人達が泣いて別れたことか。表面は名誉なことだと喜んで、親類、縁者、村人達と酒を汲みかわし、「出征帝国陸軍何々々兵」と、まず早朝から部落の神社に集まり、区長が音頭をとって万歳を三唱し、村の神社に参拝し、村の学校で歓送式を受けた後勇躍出発するのである。金沢駅から汽車に乗る場合は、村人達はあげて西金沢駅に日の丸を振って見送ったものである。
不幸にして戦死した公報が入ると、その遺骨を迎えに矢作の部落のはずれなどへ出迎えて、其白い遺骨の箱を抱えた姿に接すると、ひとりでに涙が出てなんともいえない感動にうたれたのである。
昭和二年度に発行された富奥青年団々報「双芽の報」の各部の事業報告記録の中に、「軍事部記録」というのが掲載されている。日本が戦争に突入する前哨戦の頃である。あまり珍しいので、当時の思い出として記載するが、村の青年団に軍事部という部が置かれ、専任部長がいたことがわかる。
軍事部記録
軍事部長
一、昭和二年七月二十一日
在営軍人慰問のため、在郷軍人分会と合同して午前八時小学校に集合、同時出発。隊伍整然として徒歩にて午前十一時、山砲隊に到着。同隊在宮の黒川曹長(下林出身)を訪問致し、三十分の後同隊を出発、古き歴史を有する野田道を後に歩兵第七連隊に向かった。途中にて一同昼食を取り、午後一時三十分、歩兵第七連隊に到着。各在営者に面会致し、一時間余りの後、田中伍長の挨拶をうけて同隊を出発、大手町にて一同解散す。
一、十一月二十八日
一年志願兵として千葉県国府台の野戦重砲隊第一連隊へ金田秀次君(清金出身)入営、佐久間軍事部長松任駅ま
で見送る。(注=この時の軍事部長は佐久間由秋氏である)
一、十一月三十日
本団出身の軍人、竹内一朗、久田久勝、東外吉の三氏退営のため、宮川団長以下多数歓迎に行けり。
一、十二月一日
一年志願兵として金沢騎兵隊九連隊へ藤井末吉君(粟田出身)入営す。団長以下数名、御見送りす。
一、十二月十六日
午後二時より小学校講堂において青年団主催入退営軍人歓送迎会を開催す。
除隊者 竹内一朗、久田久勝、東 外吉
入営者 中村一信、野田順一
一、昭和三年一月十日
野田順一君(上新庄出身)歩兵第七連隊へ入営のため団長以下多数御見送りす。
一、一月十六日
豊橋騎兵第二十五連隊へ伊藤好麿(下林出身、現存者)君入営のため宮川団長以下多数金沢駅頭まで御見送りす。
実に貴重な記録である。昭和二年以前もおそらくこうして入退営軍人を歓送迎したであろうし、各部落の若衆連中もこれに関連して歓送迎の宴を催したり、神社に参拝したりで、あげて混雑したであろう。と同時に、常に青年団が積極的に先頭に立って村といわず、部落といわず、主体的に行動を続けたであろうとも思われるのである。もちろん軍事面だけでなく、あらゆる発展的なことに村のリーダー的役割を果たしたことだろう。
四、愛国婦人会
日清、日露の戦いで、日本は大勝利をおさめたが、そのかげでは幾多の悲しい死傷者を出した。第九師団でも死傷者の数は二、六九二人の多きにのぼり、第七連隊はそのうち約二、〇〇〇人にも達した。こうした戦争のあとをうけて明治三十九年九月二十日、愛国婦人会が結成された。石川県では明治三十五年に既に結成されていた。
戦争が起こるごとに慰問袋や救援金の拠出などに活動し、その他留守家族の家庭訪問や、入営軍人の慰問など、婦人達の活動が注目され、喜ばれていた。
昭和七年十月頃に「大日本国防婦人会」が新しく結成され、翌八年になると県下の町村でも国防婦人会が組織され、戦時体制へと固められていった。そして服装もすべて婦人服にもんぺとなった。わが富奥村でも国防婦人会が結成され、これに参加したのである。町村では愛国婦人会と常に合同して戦時活動をしたようである。また、拠出金で飛行機などの献納も果たした。
戦争が激しくなるにつれて、昭和十七年二月二日に「愛国婦人会」「国防婦人会」「連合婦人会」などが全部解散し、「大日本婦人会」が結成され、すべて大政翼賛会の統制のもとにおかれ、聖戦完遂のため銃後の活動を続けたのである。
本村の愛国婦人会長 古源節子、副会長 中島勲子、谷 孝、国防婦人会長 中島勲子、
五、秋季大演習と村
大正十三年十月、陸軍特別大演習が摂政宮殿下を迎えて、金沢を中心に北陸地方で行われたことがある。村では兵隊を各部落に割り当てる協議が行われ、各部落では演習に参加した兵隊を家々に人数を分けて分宿してもらい、料理を作ってもてなしたものである。おびただしい軍馬などは村の広場につないで当番などを決めて見張った。主婦達は白い割ぽう着をつけて兵隊さんの料理を運んだ。
大演習は毎年秋になると始まったが、村に来て兵隊さんが泊まることはめったになかった。が、秋の収穫がすんだ頃になると、金沢第九師団の秋季機動演習が毎年のように石川平野に展開された。
大正十三年六月十七日 富奥村長印
各字区長殿
閲兵式陪観ノ件照会
本年秋季特別大演習ガ第九師団管下二於テ御挙行被為在御予定ノ特別大演習閲兵式エハ左記ノ通リ陪観許可相成筈二有之趣日本赤十字社石川支部ヨリ申承り候条陪観希望者左記各項ニ依リ御調査ノ上本月二十三日迄ニ員数会員ノ種別ヲ記載提出相成度候
追テ観閲式場地域狭少ニ付陪観着ニ制限ヲ加へラルヤモ難ク計ラルルニ付予メ御承知置相成度候
左記
一、日本赤十字社佩有功章特別社員及一般正社員委員部職員分区職員
二、愛国婦人会維持会員特別会員通常会員
この年特別大演習があり、摂政宮殿下が来られるというので、上を下への大さわざであったらしい。五十七〜八歳以上の人ならたいていの人は道に並んで見にいったはずである。赤十字へ金を寄付した人は特別の恩典があった。この頃は羽織はかまで、洋服を着ている人は学校の先生ぐらいであった。
六、血のにじむ思い出の供出米
昭和十三年に国家総動員法が制定されてから、生活のすべてが統制経済になった。食糧の統制はその中で最も大切なものであるため、すべて割当供出制となった。食糧増産が国をあげて叫ばれ、村もまた呼応してこれにこたえた。が、秋の収穫が終わっても第一次供出米、第二次供出米と冬になっても夜、常会を開いて供出米の割り当てを協議した。割り当て米を少しでも渋ったりすると国賊呼ばわりされ、時には常会の最中に泣き出す村人もいたし、徹夜で協議を続けるため倒れる人も出るなど、全くいまから見れば考えられないほどの苦しみであった。収穫量が家々によって違いがあるので、その間の調整でけんかになったり、わめいたりで、おかゆをすすっても戦争のために米を供出しなければならなかった。
そして、米の供出が割り当てに達しないと二回、三回と常会が開かれ、個人割り当てが出せない時は、多く収穫した農家から出してもらった。供出米を出せなかった農家は実に悲しい、つらい無言の侮辱を受けたのである。
大麦は田んぼ十枚から五枚を作り、小麦、馬鈴薯もまた五枚から二枚と作って、この管理がまた血のにじむ思いであった。
男子という男子が戦争にとられ、稲作などの農作業には労力が不足し、雑草などが繁茂して食糧増産をさまたげるというので、兵隊にとられた家庭には労働人員が割り当てられて助けた。金沢から男子の学生達が稲刈りなどの手伝いに割り当てられて応援にきた。
七、部落常会の活動状況
村当局の重要政策として各種団体の運営があった。農民精神の修練、食塩増産の徹底、健民運動の遂行、防空体制の確立、軍人援護事業の強化など、その達成のため村常会、部落常会を通じて挺身奉公の誠を捧げ、部落常会によって相互の理解を深め、総意を結集して透徹した。
イ、部落常会の組織
常会長は当該部落区長とし、斑長は各部落の適当な人物を常会長が指名、推薦し、会長の指示に従って隣組内を統率指導する。
各部落常会には婦人部、青少年部などを設け協力させる。
ロ、活動状況
定例部落常会
・毎月八日、大詔奉戴日の朝、各部落神社氏神に参拝し、神前行事、宜戦の詔書拝読などのあと、常会を開催、伝達および打ち合わせを神前において行う。
・臨時部落常会
村常会のあと緊急協議伝達を要する必要ある場合において行い、「上意下達」の敏速徹底を期する。
・労働問題
春季の水田耕耘作業、田植え作業、秋季の稲刈り作業、稲こき、うすすりなど労力不足を調整し、一村一心の村長に基づいて余剰労力の活用に当たる。
・共同作業
増産目的達成と、一円融和の実をあげるため常会の指令に基づき、春秋の農繁期の作業はもちろん、冬季間のわら工品作業に至るまで一堂に会し、たがいに協力して行う。
・勤労奉仕作業
部落常会、婦人部、青少年部で農事試験場、陸軍病院、その他各地の勤労奉仕運動に卒先参加する。
・増産協力
家畜の飼育、堆肥の積み込み、麦作奨励、そば、きび、大豆、甘藷、馬鈴薯などの栽培を励行し、空閑地をなくし、その供出を奨励徹底し、活発に行う。
・国民貯蓄の励行
各戸別に国民貯蓄の義務額を指示し、実践にうつし、さらに国債などの割り当てに対しても協力して購入消化する。
・銃後の後援
出動将兵遺家族および戦没者将兵遺家族に対しては、春秋それぞれ適当に繁忙期を見計らって、常会として適切な援護をする。なお婦人部、青少年部も稲刈り、稲こき、落穂拾いなど適当な作業に出動する。
・物資の配給
節約と勤倹質素の美風は経済更生運動実践当時から培われた村風で、増産目的達成のため肥料、石油など有効適切に使用し、衣料、薪炭、食料品その他の配給に対しても不平、不満をいうことなく、あまんじて国策に随順する。
・その他
なにごとも発生することは右に準じて常会にはかり、適切、敏速に処理し、徹底を期する。
・実情と役場事務
国家の発展と大東亜戦争完遂のため、役場事務は石川県訓令甲第二十四号、町村役場処務規定要項により、現在の人員をもって、粉骨砕身務めるのはもちろん「月月火水木金金」の精励をもって卒先職務に当たる。
八、健民運動の推進
戦時体制下、食糧増産につとめ、しかも青壮年層が戦争に多数動員されているとき女子青年婦人の勤労時間はどうしても多くなった。そのため、健全な母体の維持にひずみができ、次の時代をになう幼児、乳幼児の健康をそこね、その死亡率が高くなるおそれがあった。本村ではこうした心配に対応、健康の増進、栄養の保全、体位の向上、疾病の治療など健民施設の万全を期すため、村当局が中心となって、学校や各種団体と協力して左記施設の実践につとめた。
・乳幼児体力検定
厚生省の定めるところに従い、健康保険医数名の検定を受け、あわせて健康相談や疾病診察を行い、乳幼児の保護救済の一助とする。
・健康更生診療
大日本婦人会富奥村支部を後援して、母体や乳幼児の健康更生を図るため、内科、産婦人科、小児科などの各専門医を招いて精密検査を行い、強健な母体の維持、産前産後の保健新生、乳幼児の養護育成などにつき懇談する。
・妊産婦調査及び栄養剤給与
各部落婦人部班長が妊産婦を調査し、その氏名を報告、産前産後の保健衛生指導要項を与え、さらに栄養補給剤を給与して母体と乳幼児の保護に当たる。
・母子保護指導
助産婦を派遣して妊婦あるいは産後婦人の指導に当たらせる。
・栄養料理講習会
農繁期前、農家繁忙時の栄養料理に関する講習を開き、労働と栄養補給の関係について実践励行させる。
・婦人衛生講話
毎年七月、十一月、二回国民学校を借りて行う。
農繁期には幼児の栄養と健康がややもすると不十分になるのと、労力不足になることを補うため、春秋二期、四十日間、保育所を開設する。
・学校給食
国民学校は婦人会と協力し、児童の中食時の栄養を増強する目的で学校給食を行い、効果をあげる。
昭和十七年に村で決められた活動を記すと次のとおりである。
一、防空体制の確立
国土防衛の大任は山間僻地といえども、かかって銃後国民の双肩にあり、裏日本の中枢金沢に近い当村は、北に備え南を慮りて、ここにいよいよ防空体制の強化を拡充し、左の防衛施設に全力をあげる。
・警防団の活動
警戒警報中は警防団本部にて昼夜監視および警備をなし、全村に警戒網を張らしめて警戒員を出し、警戒体制の徹底を期す。
空襲警報至るや全員出動、ただちに出動体制をとり敵機に備う。
・部落防衛団隣保班の活動
警戒警報発令中は各部落における防衛団および隣保班より、各々防備員を交替出動せしめ、各部落の燈火管制、防空資材の配備状況点検等、事前にこれら防衛体制の完壁を期きしめ、空襲警報発令なるや警防団と協力して各々その任務につく。
各戸に必ず左の資材を用意し、防衛体制に備える。
資材 砂のう二〇個 むしろ十枚 はたき三本 水そう二個 ばけつ三個
装置 暗幕装置 (全家屋を完全におおうことが出来る分量)管制用電灯おおいその他
・警報伝達及び監視
警報電話をもって村役場に通報あり。役場係員はただちに警報台上に標識旗を掲揚し、全村に通告す。
警防団員監視に当たり、その後の状況につき凝視し、異状を認めたる場合ただちに役場本部と警防団本部に通報す。
・村重要機関の防衛体制
国民学校における防衛体制は、まず御真影の警備を厳にするため、講堂に資材を整備充実し、その他玄関や校舎の左右に資材を左記個数をそれぞれ配置する。
砂のう三十個 水そう一 バケツ十 むしろ五 はたき五 つき棒三
以上を一組とし、校内六個所に配置する。
さらに校舎ガラス窓の破損にともなう損傷破壊などを防ぐため、テープ張りを徹底して行う。
学校防衛団を組織、各週水曜ごとに訓練を行う。
産業組合、役場、その他国民学校の隣接建築物においても、国民学校と同様の管制装置、防火資材の用意をする。
二、軍事援護事業の強化
大東亜戦争完遂のためと出動将兵、戦没将兵に感謝を捧げるため、左記のとおり施設、行事を行う。
・戦没将兵家庭法要
銃後後援会で村の僧侶全員の出動を得て、各家庭を巡回、読経供養する。
・出動将兵遺家族勤労奉仕
村当局をはじめ、婦人会、男女青年団、国民学校児童、さらに各部落割奉仕隊で農繁期に動労奉仕隊を繰り出す。
・労力調整令の活用
各部落の全労働力をもって各戸の作付け反別に応じ、比例配分式に労力の合理的分割をなし、出動将兵の家庭に対して保護援助をなす。
・保育料金の免除
出動将兵の家庭における幼児の保育料は免除する。
・遺家族慰安会
男女青年団、国民学校児童に行わせる。
・忠魂碑招魂祭
毎年七月七日(当時はこのようになっていた)を定日として村民一同碑前に会し、仏式をもって行う。
・銃後奉公会の活動
村長自ら銃後奉公会々長となり、軍人援護事業を遂行する。
・軍事援護相談所の活動
出動のため生計困難なもの、戦没のため遺家族の混迷窮乏なものを保護救済し、授産方法も講じて活路を与える。
・慰問袋の発送
出動将兵に対し、年一回慰問袋を各種団体合同で発送させる。
・国民貯蓄の協力
二百三十億円の貯蓄目標達成に協力すべく村常会を開催、各村常会構成員が全員協力して国家の目的達成につとめる。
昭和十六年八月に石川県から代謄写として国民貯蓄組合法(昭和十六年三月十三日、法律第六十四号)という小冊のパンフレットが各字までに出ている。戦争を勝ち抜くために貯蓄をいかに奨励したか、その内容は命令的となっている。
その中に「国民貯蓄組合法ナラビニ同法施行ニ関スル命令ノ実施ニ関スル件依命通牒」というのがある。
各字ではこれらにもとづいて苦しい中から貯蓄を割り当てられたのであった。
九、配給制度と割り当て
日清、日露戦争の銃後もやはり国をあげての戦時体制だったのだろう。明治天皇が「おきなやひとり山田もるらん」とうたわれたことによっても、その苦しい銃後がうかがえる。昭和の戦争もいよいよ長期戦となり、物資は配給制となり、隣組制度によって分配され、割り当てされるようになった。
昭和十六年には平和産業が全部軍事産業に変わり、軍隊以外の男子は徴用令によって軍事工場にとられ、女子もまた挺身隊員という名目のもとに神奈川方面の軍事工場に動員された。村の女達は食糧増産に励むかたわら割り当てられた軍馬の草刈りと、その乾燥作業やらに追われた。また、松根油の供出で近くの山へ松ヤニの採取や海岸での塩づくり作業に出かけ、老人達といっしょに働いた。
軍事債券などの割り当てもまたきびしく、各農家に割り当てて金を出させた。
その頃になるともう村の家々にある火ばちや指輪、仏具まで、金属という名前のものはすべて供出しなければならなくなり、火葬場の鉄扉までも切りとって供出に応じたのである。また、戦争に勝つために、国民精神総動員の日など決めて、毎月各字ごとに村人連が早朝、神社に集合して参拝し祈願をこめた。つごうで欠席でもすればただちに国家に非協力的と非難をあびた。
十、共同炊事
食糧が供出され、統制され、配給制になっても、戦いに勝つためには食生活を改善し、共同炊事にしなければ健康をたもてないということで、村の婦人会では当番を決めて共同炊事場をつくり、昼と晩の副食をつくって各農家に配給した。バケツを持って順番を待っておかずをもらいにいったのである。
だから、村の各家々は全部同じおかずで食事をした。楽しいようであり、無味乾燥でもあったが、そんなこともいえずに暮らしたのである。金沢から女子師範の学生までが割り当てられて共同炊事を手伝った。
昭和十八年から十九年になると、戦争は激烈になり、各島々では兵隊が玉砕し、アメリカ軍に占領され、B29爆撃機が日本の都会を毎晩のように空襲で焼き払い、尊い人命や軍需工場がつぶされていった。
昭和二十年八月六日に広島市に原子爆弾が投下され、続いて八月九日、長崎市にも投下され、一瞬にして何十万の市民の生命が絶たれた。世界戦争史上初めてのことである。
十一、切符制と点数
その頃から調味料や衣料品もすべて切符制となり、それぞれ通帳が発行され、みそ、しょうゆ、砂糖、塩などは少しか買えなかった。衣料品もまた点数制となり、手ぬぐい一本、地下たびなども一足とされて点数を切られた。
一家族一〇〇点とされ、嫁入りなどの場合は親類などが点数を持ち寄ったのでがまんをした。
点数の例をあげると、みそ百匁、しょうゆ五合、衣料品の国民服32点、学童服17点、もんぺ12点、縫い糸一〇匁などで「ほしがりません勝つまでは」の合い言葉で古い着物などをおろしてもんぺにしたり、男子ほ国民服に巻ききゃはんとなった。物価はすべて統制され、値段も決められて、高く売ることは禁止された。物品に全部丸公の標示をつけて、これに違反すると罰せられたのである。
都会では防空濠が掘られ、各家庭は厳重な灯火管制を行い、わずかな光でも洩らしたらきつく注意された。
サイレンが鳴ればただちに当番の村人が「空襲警報発令」とか「警戒警報発令」と告げて回り、乳児などをかかえた家庭では真っ暗で育児に困ったものである。
ガラス窓は全部紙を縦横に張り、真っ黒なハトロン紙か、カーテンを買って窓に下げて、光が洩れないようにした。もちろん電灯には黒い垂れ下がった笠がかぶせられた。
この頃から都会では疎開が始まり、親類縁者を頼って荷車に家財道具を乗せて運び、村の各家庭はごったがえしたように忙しくなった。
その頃、金沢市四十万の山にやぐらを組んで交替で飛行機を監視する監視所が軍の命令で出来た。割り当てで兵役にいかない若い男子がこれに当たったらしい。英語はすべて使用を禁止された。
十二、敗戦と復員
昭和二十年八月十五日、照りつけるような真夏の旧盆の正午、天皇陛下の直接の言葉がラジオを通じて全国に放送された。「重大ニュース発表」がそれである。米国、英国、ソ連、中国などの決めたポツダム宣言によって、日本は歴史上かつて経験したことのない無条件降伏を受諾したのである。
終戦とは体裁のよい言葉である。血みどろになって戦い、金属と名のつく家財道具まですべてを供出で失い、戦災都市の人達は生命まで失い、身体一つ助かったのがやっとであった。敗戦のときの日本の陸、海、空軍の総兵力は七百二十余万人だったといわれ、太平洋戦争だけの戦病死軍人の数は二百万人以上とされている。除隊軍人などを含めると、この戦争だけで約一千万人にのぼる兵士が戦争に参加したのである。これは当時の男子全体の四分の一に当たり、世帯数からいうと二世帯に一人強という男子を軍人として送り出した。
こうして日本はこれ以上焦土とするにしのびずとの天皇陛下の一言で長い間の戦争から解放されたのである。
わが村でも多くの若い人達を戦争で失った。遺骨となった人や、南洋や大陸で戦死し、海の藻くずとなって遺骨も届かずに、一片の紙切れで戦死を知らされ(これを戦死の公報といった)、爪と頭髪だけで村に無言の復員をした若い人達もいた。生き残った兵士たちは二十年八月下旬から十二月までに続々と村へ復員して来た。内地部隊に属していた者の復員は早かったが、海外に抑留された者の復員は遅かった。とくにソ連に抑留された部隊は何年も労働に服した。
身体の弱かった者は抑留中に死んでいった。「異国の丘」などの切実な流行歌が出たのもこの頃である。
十三、敗戦とヤミ物資
昭和十九年から二十年にかけて毎日のように続けられたB29の都市空襲によって、軍事施設、港湾など、まさしく日本列島は焦土と化し、火の海となった。富山市も二十年八月一日の空襲で廃虚となった。石川県だけは幸いにして空襲をまぬがれ、そのままの姿で終戦を迎えた。
終戦と同時にインフレとなり、復員軍人や引き揚げ者で人口はふくれあがり、生活物資は不足し、買い出しに狂ほんする不安な社会情勢が続いた。
米の生産県である石川県でも、戦争中の昭和十九年で一・五?(一升)六十二銭の米が、二十年十一月には三円にあがり、二十一年三月には三十五円、七月には五十円と驚くほどの急カーブで上がり続けた。
二十一年の十一月には主食である米の配給が成人で三五五グラム(二合五勺)となったが、それまでは二合一勺(二九七?)で、一食当たり茶わん一杯の量がやっとであった。腹がへってどうすることもできず、大根の葉やさつまイモのつるなどほ引っぱりだこで、細くきざんで米とまぜて雑炊にして食べた。
街頭では雑炊を切符制で売り、一杯を食べるのに行列をつくって寒空に順番を待った。
さつまイモや大豆かすなどが主食代用として配給されると、その分だけ米が減らされ、野菜の配給などは一日一人当たり七五グラム。魚は四日か五日に一度、それもなれたイワシ一匹ていどがやっと手に入り、役場の配給係りを通じて各区長あてに何日の何時まで取りにくるようにと通知が出された。もっと悲惨なのは街の人達であった。子供をかかえた母親達はヤミ食糧品の買い出しで朝から遠くまで歩いて出かけ、農家の庭先に立って、大切な着物などと交換してまで食糧を求めた。
農家もまたひそかに米やイモなどを着物や珍しい物と交換し、一時はそれを商売にする人まで出た。背中一杯にかついで帰る夕方頃に警察官に見つかって逃げた人もたくさんいたし、その頃の農家の人も街の人も必ず一度や二度は苦い経験を味わったはずである。金沢から京都や大阪などへ買い出し列車が出たのもその頃であった。
ヤミ米を原料にして酒を造ったり、あめをつくったりすることも盛んに行われた。ショウチュウや合成酒が出たのもこの頃であった。
二十一年一月頃、金沢駅の乗客は一万一千人以上にふくれ上がり、そのうち八千人は女を中心とする買い出しの人で占められたという。いま思っても想像出来ないほどのひどい時代が続いた。その食糧難とインフレは昭和二十四年中頃まで続き、諸物価は大正末期の三ヵ年平均にくらべると実に五百三十倍となってしまった。
こうして苦しい敗戦のショックと、食糧難と、インフレと失業とにあえぎながら、村人達は懸命にこらえ、耐え忍んで米の生産に励んで来たのである。昭和二十五年頃からようやく敗戦の混乱期とヤミ価格から脱し、少しながらでも生活に落ちつきを取りもどして来た。
十四、内原訓練所と農業報国推進隊
戦争が激烈となり、戦域が拡大されるにつれて、食糧の増産が叫ばれた。その頃、加藤寛治や石原莞爾らによって食糧増産を図るために、農業報国推進隊なるものを全国各県で結成し、茨城県吾妻郡内原に満蒙開拓義勇軍訓練のための日の丸兵舎が大規模に設営されてあった。その内原訓練所へ一ヵ月から四十日はど入隊し、食糧増産や心身の鍛錬を目的に集団訓練を受けた。
各県から五、六百名、全国から一回に二万名〜三万名近くの青年を内原に集めて、軍隊式に訓練を受けさせるのである。各市町村長の推薦を受けて参加するのである。わが村の場合、当時内原へ四十日ほど家を留守にして参加することは生活に直接響くことで、初めは参加者がいなかったが、一人が先に参加を希望したことから全部で八名が参加することになった。昭和十五年十一月のことであり、第一回内原訓練所への入隊である。
第一回参加者氏名
石川中隊第一小隊長 竹内一朗(粟田) 隊員 村太武範(太平寺) 中野助盛(粟田) 村井幸次郎(上林)
西村善吉(末松) 松本弘文(末松) 上野由雄(清金) 中島潔(太平寺)
村の人達の盛大な壮行式にのぞみ、勇躍して内原に向かった。中島潔氏はさらに六十日間ほど残留し、農村の共同炊事や栄養学を受け、満蒙にも渡って活躍した。四十日間は日課によって訓練を受け、夜は討論などで勉強した。なんといっても内原訓練所の営庭で、全国から集結した二万五千の隊員が整列した時の光景や、中島栄治氏が県を代表して一週間ほど内原に来て、時の石黒忠篤農林大臣と一緒に石川中隊を訪問された感激はいまも忘れられない。これらの隊員は村へ帰って食糧増産の第一線に立ったことはいうまでもない。
それから毎年十一月頃、内原訓練所へ村から青年達が十名内外が派遣されて、食糧増産に励み、十八年頃まで続いた。参加隊員の中にはさらに満州の広野にまで全国から選抜されていった人もいた。
十五、満蒙開拓青少年義勇軍
昭和十二年頃になると、日本は満州を守るために関東軍はもとより各師団から軍隊を駐とんさせて権益を守ったがさらに石原莞爾や加藤寛治らによって満蒙の地に開拓義勇軍を送り、軍隊と呼応して農業を営みながら銃をとる方法で、続々と満洲に派遣したのである。その訓練所が内原であった。国民学校を終えたばかりのまだあどけない少年達を全国から選抜して、何十万と満蒙の地に送って、国境警備と開拓にあたらしめたのである。
昭和十三年三月一日、わが富奥村から満蒙開拓青少年義勇軍として次の四名が参加した。
山田佳吉 中野喜佐雄 香城清雄 五香 晃 藤田報恩
学校の校庭に小学校はもとより、村民多数参加して盛大な歓送別式を挙行し、まだ幼さの残る十五、六歳の四少年の前途を激励し、粟田駅まで全員見送り、別れを惜しんだ。
こうして義勇軍を終えて、そのまま開拓農民として残り、大東亜戦争がきびしくなった昭和十九年頃から、それらの義勇軍や開拓農民の人達はほとんど現地召集令を受けて戦争にとられ、抑留されたり、戦死したりしたのである。
いまにして追想すれば、これらの人達はまさに戦争というしくまれた渦中に踊らされた一片のはかない犠牲者なのである。
十六、忠魂碑
国運をかけて戦かった幾多の戦争で若い生命を犠牲にした人達の霊をまつる石碑である。わが村では次のような通知が出ている。
富特第二九四号
富奥村長 印
大正十年八月二十五日
殿
自治会組織並紀念碑建設 等ノ件ニ関シ招集方
通牒 (三納 佃 栄吉保存)
今回本村ニ於テ自治会組織並ニ戦病死者紀念碑建設等ノ件二関シ御協議申上候間来ル八月二十七日午後三時不遅当役場へ御参集相成度此段及通牒候也。
現在の忠魂碑は公民館と保育所の間の中央道路に面して、東を正面として砲弾型の堂々たるもので、総御影石でできている。高さは道路上から十?、台の高さが一・五?で、その上にさらに四・五?ほどの台があり、その上に高さ四?ほどの砲弾型の円錐のみがき御影石が空に向かって建っている。忠魂碑の前には両側に四角い黒御影石の平板に戦死者の名前をきざんで掲げてある。丸い一?ほどの御影石の花立てと、高さ一・五?ほどの灯ろうと、いずれも一組ずつ、昭和二十七年八月、上新庄出身の庄田和作氏の寄贈で建てられている。道路ぶちの大灯ろうはあが村の復員して来た全員の心ばかりの寄付によって建てられた献灯である。
道路から向かって右の水銀常夜灯は、終戦二十年記念として昭和四十年八月建之、として山田一郎、谷好信、吉本栄松の三人で寄贈されたものである。
向かって左の緑濃い赤松は元富奥小学校の校庭にあったものであり、また向かって右のキンモクセイも校庭の中央正面玄関入り口の築山にあったもので、ともに思い出の立派な木である。戦友達もこの木を見ながら静かに眠っているのである。忠魂碑の真ん中にきざまれた碑文は
加賀国石川郡富奥村人相謀日今茲戊辰秋今上将挙即位大礼草□下民幸逢斯盛典写可以来慶賀之口而伝諾永遠衆皆
同輩日興以来朋兵数次死亡不可勝紀然無奮起邦家之難此躯於難鴻毛之軽者為観興口皇運之隆昌哉我郷従清露二役
致命君国者可九人英其忠勇義烈真可謂百代之亀鑑也乃之立豊碑以弔英魂伝後世子孫感観興□和報茲□任務而忠死
者□則并勤其氏名以彰功不亦可乎於是建□□村中形勝之地来求余銘銘目□□聖論有言義勇奉公拳拳服膺□厥□後
人志宣揚 皇国 宝祚隆 天壌無窮
昭和三年八月
従四位勲四等 赤井直好 揮
従四位勲四等 岡本 勇 書
となっているが、大正十年八月の通知のようにその後紀念碑が建てられたかどうか記憶がない。現在の忠魂碑は昭和三年に建てられたものである。従って昭和になってからの戦争に関した碑文となっていない。
わが村の青年団はこの忠魂碑が建てられた八月七日を記念して盆踊りを行って来たが、戦後長く中断していたのを昭和四十三年に藤多隆青年団長によって復活し現在も行っている。
十七、富奥遺族会 (西田入六会長調べ)
昭和二十年十一月三日発足。大東亜戦争(第二次世界大戦)においてわが子、夫、親、兄弟を国家に捧げた同境遇のわが村の人達が相寄り、相助け合い、慰め合うことを目的として会を結び、物資不足の折柄、粟田浄福寺においてローソク、油等を持ち寄って慰霊法要を行ったのが発足の初めである。当時会員数は三十三名。会長に藤田敬治氏を選任した。県内遺族会の最初といわれる。
昭和二十五年十一月、秋季慰霊法要後規約を定め、日清戦争以後の遺族を含めて会員数六十三名となる。
昭和二十七年遺族年金受給者十七名、遺族国庫債券受給者十名。
昭和二十九年公務扶助料受給者三十三名。
昭和三十年三月、公務扶助料受給と同時に総会において規約を改定し、戦没者の追悼、会員相互の扶助ならびに平和日本の再建と、地域社会の発展に寄与することを決める。昭和四十九年現在、転入者など会員増加となり七十八名となる。県営百々鶴荘在住者に二十三名を数えられる。
歴代会長名
昭和二十年〜二十三年 藤田 敬治
昭和二十四年〜二十五年 中島六三郎
昭和二十六年〜二十七年 高橋 吉次
昭和二十八年〜三十年 中島六三郎
昭和三十一年〜三十四年 高橋 吉次
昭和三十五年〜三十六年 西村 久勝
昭和三十七年〜三十八年 高橋 吉次
昭和三十九年〜四十三年 蟹川 清政
昭和四十三年〜四十七年 長井 太吉
昭和四十八年〜現在 西田 入六
十八、軍人恩給連盟(略称軍恩) (五香益喜会長調べ)
富奥分会
軍隊に入隊し長い年月を戦争に参加された方々に対して恩給が下付される会の名称である。もちろん全国段階から石川県と組織されている。富奥分会の結成は昭和二十八年七月である。
歴代分会長氏名
山田一郎 昭和二十八年〜三十一年
大島直吉 〃 三十二年〜三十四年
高納友春 〃 三十五年〜三十六年
谷 好信 〃 三十七年〜四十 年
林 与吉 〃 四十一年〜四十六年
五香益喜 〃 四十七年〜現在に至る
普通恩給会員
氏 名 陸海別 兵 科 階 級
山田一郎 陸 軍 歩 兵 曹 長
安田庄一 〃 近衛歩兵 曹 長
金村信哲 〃 衛生兵 伍 長
川越正雪 〃 歩 兵 伍 長
西村敬親 〃 歩 兵 伍 長
浦 秀雄 〃 歩 航 中 尉
藤田敬温 〃 輜重兵 上等兵
北村信一 〃 歩 兵 曹 長
吉本 章 〃 歩 兵 二等兵
香城 学 〃 歩 兵 軍 曹
西田入六 〃 騎 兵 曹 長
藤井 克 海 軍 水 兵 上 曹
橋本初治 陸 軍 歩 兵 伍 長
堀江秀吉 〃 歩 兵 曹 長
山原栄吉 〃 砲 兵 曹 長
大島直吉 〃 歩 兵 軍 曹
伊藤好暦 陸 軍 騎 兵 曹 長
山田由次 〃 輜重兵 上等兵
長 忠雄 〃 輜重兵 兵 長
杉野 博 〃 歩 兵 兵 長
林 与吉 〃 歩 兵 伍 長
作田庄一 〃 歩 兵 伍 長
諸角善一 〃 歩 兵 少 佐
平野 正 〃 歩 兵 曹 長
平井 清 〃 砲 兵 兵 長
三口俊秀 〃 砲 兵 曹 長
北岸文雄 〃 歩 兵 軍 曹
五香益喜 〃 歩工船 軍 曹
川畑良章 〃 砲 兵 曹 長
町谷直春 〃 歩 兵 兵 長
計 三〇名
一時恩給会員
村井幸次郎 陸 軍 歩 兵 軍 曹
村本 外堆 〃 歩 兵 軍 曹
新森 晃 〃 歩 兵 軍 曹
松本 繋 〃 歩 兵 中 尉
計 四名
扶助料会員
村井 利八 海 軍 水 兵 一 曹
村井 三良 陸 軍 輜重兵 上等兵
野田 順一 〃 歩 兵 准 尉
谷 好信 海 軍 水 兵 上 曹
久田 久勝 陸 軍 歩 兵 曹 長
沢村 庄松 〃 憲 兵 伍 長
伊藤仁三郎 〃 歩 兵 伍 長
高納 友春 〃 砲 兵 兵 長
計 八名
尊き英霊をたたえる (七八名) (遺族会調)
兵科 階 級 戦死者氏名 戦死 年 月 日 戦 病 死 場 所 部落別
陸軍 憲兵上等兵 杉内初三郎 明治二八・七・二四 日清戦争清国大孤 上新庄
陸軍 上 等 兵 橋本鉄太郎 明治三七・ 八・二一 万竜山 下 林
陸軍 上 等 兵 中村茂三郎 明治三七・ 八・二一 万竜山 粟 田
陸軍 一 等 兵 古源七三郎 明治三七・一一・六 遼東半島八巻山 末 松
陸軍 伍 長 沢村与十郎 明治三七・一一・二六 万竜山 下 林
陸軍 上 等 兵 中村駒太郎 明治三七・一一・二六 旅順口砲台付近 末 松
陸軍 軍 曹 小林 信二 昭和一二・一一・一五 江蘇省第三野戦病院 上 林
陸軍 上 等 兵 北井栄次郎 昭和一二・一一・ 七 承家橋付近 矢 作
陸軍 上 等 兵 市村 謙治 昭和一三・四・二〇 安徽省磨盤山附近 粟 田
陸軍 軍 曹 上田 敏夫 昭和一三・一〇・一〇 湖北省陳安竜東方 上新庄
陸軍 伍 長 中島 賢次 昭和一三・一二・一 江蘇省黄渡鎮 太平寺
海軍 一等水兵 長 巌 昭和一四・五・一四 横須賀海軍病院 下 林
陸軍 上 等 兵 山原 信導 昭和一五・四・二八 広島陸軍病院 矢 作
陸軍 中 尉 村田 利久 昭和一六・一・九 河北省白荘付近 藤平田
陸軍 憲兵曹長 西尾 由堆 昭和一七・ 八・一五 姫路陸軍病院 上新庄
陸軍 兵 長 藤井 実 昭和一七・一二・一七 篠原陸軍病院 藤平田新
海軍 主計兵長 浅井 正男 昭和一八・ 二・ 八 本州南方海上 粟 田
陸軍 少 尉 香城 光磨 昭和一八・ 五・二四 東京第二陸軍病院 粟 田
海軍 二等機関曹長 越田 清司 昭和一八・九・二七 ソロモン諸島フロレス海方面 上新庄
海軍 兵 曹 金田 茂二 昭和一八・一〇・ 二 フブライス諸島 中 林
海軍 上等水兵 四ツ井清蔵 昭和一八・一〇・一山西省大原 新 庄
海軍 上等水兵 舘 外光 昭和一八・一一・一一 ソロモン沖海戦(旧姓河村) 中 林
陸軍 兵 長 大島 豊次 昭和一九・一・一六 南太平洋上 三 納
海軍 上等機関兵曹 山田 俊堆 昭和一九・ 三・一五 ニューギニア方面 三 納
陸軍 一等 兵 北村 好次 昭和一九・ 四・ 七 印度カソム方面 下新庄
陸軍 兵 長 藤田 報恩 昭和一九・四・一五 ビルマ作戦トンポ方面 上新庄
陸軍 上 等 兵 津田 茂明 昭和一九・ 四・一八
陸軍 中 尉 高橋 政雄 昭和一九・ 五・ 六 ビルマ作戦イタインギ方面 上新庄
海軍 二等兵曹 佃 啓三 昭和一九・ 五・三一 アリューシャン洋上方面 三 納
海軍 上等機関兵曹 中井 章 昭和一九・ 六・一九 ソロモン沖海戦 粟 田
航空 整備上等兵 原 勝平 昭和一九・ 六・一九 中部太平洋方面 上 林
海軍 上等水兵 小林 博 昭和一九・ 六・二九 フィリピン岬方面 中 林
陸軍 軍 属 林 藤一 昭和一九・ 七・ 三 ウオツゼ島方面 中 林
海軍 二等兵曹 北村 良三 昭和一九・ 七・ 八 南洋サイパン島付近 末 松
陸軍 伍 長 北村 文夫 昭和一九・ 七・一三 河南省州楽駅付近 末 松
陸軍 上 等 兵 細基 忠蔵 昭和一九・七・一五 中支作戦
陸軍 伍 長 中西 什馬 昭和一九・ 七・二七 ニューギニヤ上陸 中 林
海軍一等兵曹 本 正二 昭和一九・ 八・ 四 小笠原方面 下 林
陸軍 伍 長 川畑 弘 昭和一九・ 八・四 ニューギニヤマフア島方面 末 松
海軍一等兵曹 島 勤 昭和一九・九・ 八 フィリピン付近 中林丸の内
陸軍 上 等 兵 土田 勉 昭和一九・九・二一 マニラ市方面 下 林
陸軍 伍 長 近宗 宗義 昭和一九・一〇・一八 マニラ沖 上 林
海軍 二等兵曹 新明 豊吉 昭和一九・一一・ 二 フィリピン方面 粟 田
海軍 二等兵曹 小林 正男 昭和一九・一一・ 七 東支那海方面 中 林
陸軍 軍 曹 土田一二郎 昭和一九・一一・二四 南洋ミレー島方面 下 林
陸軍 上 等 兵 中村 末男 昭和一九・一二・二〇 下志津陸軍病院 矢 作
陸軍 軍 属 西村 久悳 昭和二〇・一・二〇 上海付近海上 中林丸の内
海軍 上等水兵 小寺 芳雄 昭和二〇・一・二六 フィリピン海上方面 中 林
陸軍 軍 曹 古島 茂忠 昭和二〇・一・二九 台湾海峡方面 下 林
海軍 見習士官 藤井 毅 昭和二〇・ 二・二五 金沢陸軍病院 粟 田
陸軍 大 尉 金田 秀次 昭和二〇・ 三・ 四 フィリピン、コレヒドール要塞 清 金
陸軍 兵 長 長田辰三郎 昭和二〇・ 三・ 五 サイゴン野戦病院 三 納
陸軍 上 等 兵 西田 清吉 昭和二〇・ 三・九 金沢衛戌病院 粟 田
海軍一等兵曹 島崎 政明 昭和二〇・三・二七 南洋マリアナ諸島 上新圧
陸軍 上 等 兵 宮本 義夫 昭和二〇・三・三〇 静岡九三師団第四病院 矢 作
陸軍 曹 長 福田 他吉 昭和二〇・四・一一 フィリッピン秋風山戦闘 中 林
海軍 少 尉 作田 豊 昭和二〇・四・二四 ミンダナオ島クラノリ地区 上新庄
陸軍 上 等 兵 宮本 八郎 昭和二〇・五・三 熊本陸軍病院 矢 作
陸軍 伍 長 石尾 哲 昭和二〇・六・二 湖南省株州駅方面 太平寺
海軍一等兵曹 六田 忠雄 昭和二〇・六・二〇 南洋ウエキ島方面 太平寺
陸軍 兵 長 仏田 正明 昭和二〇・七・一比島レイテ島カンギボット山 上 林
陸軍 伍 長 作田 正男 昭和二〇・七・ 三 マーシャル群島ダイリ南方面 下 林
陸軍 航空軍曹 北川 利治 昭和二〇・ 七・一〇 関門海峡上空 下 林
陸軍 伍 長 高木 政幸 昭和二〇・ 七・二三 プーゲンビル島ミオ河付近 末 松
陸軍 軍 属 中野 一竹 昭和二〇・ 七・二八 比島サリオリ付近
陸軍 伍 長 多村 俊雄 昭和二〇・ 八・七 トラック島夏山方面 上 林
陸軍 軍 曹 三納 利雄 昭和二〇・ 八・九 満洲東寧阿治方面 藤 平
陸軍 伍 長 蟹川 正富 昭和二〇・ 八・一七 湖南省南湖州方面 末 松
陸軍 伍 長 長井 弘 昭和二〇・ 八・一八 牡丹江林方面 粟 田
陸軍 上 等 兵 金田 松男 昭和二〇・ 八・二四 南ボルネオ方面 中 林
開拓団員 小林外喜男 昭和二〇・ 八・二六 満州開拓団馬柘県亜河 中 林
海軍 水 兵 長 山口 芳雄 昭和二〇・一一・二一上海第一海軍病院 粟 田
陸軍 上 等 兵 平野 政雄 昭和二一・一・一五 ソ連第三〇九九病院 太平寺
陸軍 兵 長 白山 敏夫 昭和二一・ 二・二五 ソ連チタ州カグラ地区第五号 太平寺
陸軍 上 等 兵 高納 実 昭和二一・ 八・二二 後藤病院 位 川
陸軍 憲兵伍長 北岸 博 昭和二一・九・一 平壌陸軍病院 清 金
陸軍 伍 長 竹村 祐二 昭和二二・五・二五 金沢衛戌病院 粟 田
従軍 看 護 婦 平野千代子 昭和二三・四・二七 ハルビン中央病院 太平寺
わが村から戦争に参加され、不幸にして戦死、戦病死された人は 日清戦争一名 日露戦争 五名 支那事変 七名 大東亜戦争 六十五名となっている。その親達、遺児達、妻連、兄弟姉妹達が、国に捧げた生命とはいえ、長い年月をどんなにか苦しみ耐え、悲しみに泣き続けてこられたことでしょう。敗戦から三十年の歳月が過ぎ去り、尊い犠牲となられた人達もともすれば忘れがちとなってしまった。とくに若い世代の多くの人達には「われわれと関係がないんだ」というような考えの人があるように思う。若い人も老いた人も、いま一度静かに自分の存在をかみしめて、生命を犠牲にした人達の霊に深く黙とうをささげて英霊をいつまでもたたえたい。
その他兵役に関係した人
中 林 小竹徳次郎 小林繁良 山本茂雄 北本栄吉 林竜賢 山崎太之助 河村孝一
粟 田 田中忠信 中野佐之吉 竹村六三郎
上新庄 上田衛親 高橋吉次
下 林 本乙次郎 沢村与四郎 伊藤協 東省三 作田与三郎 葭田徳次郎 新森忠信 長与七
太平寺 中島一孝
清 金 中野昌次 宮岸清 藤田勝政