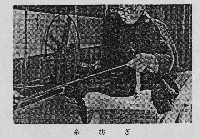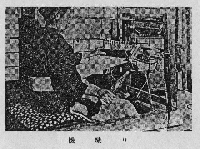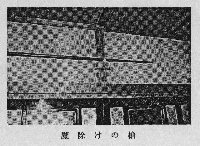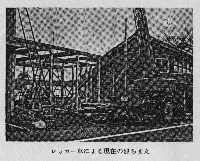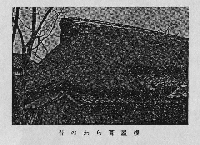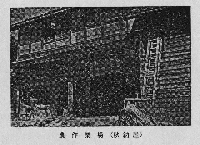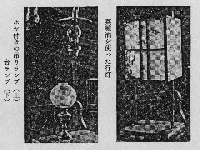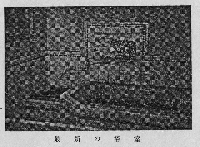[part1]
第十七章 村人の生活
==第一節 家々のくらし==
第一節 家々のくらし
一、一日の立ち居振る舞い
昔の人達は随分早起きした。「早起き三文の得」のことわざのとおり、時計の時刻より夜明けの暁光が起床時刻であった。一番先に嫁が起きる。あまり早いと暗くて灯を使うから、東の山際が白けて明暗が薄々判別出来る頃である。まず火種を起こし、食事ごしらえにかかる頃、姑も起き、続いて男達も起きてくる。男達は朝前仕事にかかるが女達は食事や家事、育児の仕事にかかるのがふつうで、姑が元気で農作業が忙しい場合は嫁も男達に従った。また、遠い田んぼ仕事や水田仕事の場合、朝食(あさい)に帰宅しなければならないから、もっくり朝食と称して朝前仕事に出る先に朝食をすませて田んぼ仕事に出た。正午の時刻は仕事中わからなかったが、日清、日露戦争後は正午に尾山(金沢の尾山城跡)のドン(大砲の空砲)が鳴ると昼上がりした。嫁が急いで帰宅すると、つぶら(いずみ)の中の幼児は息が切れんばかりに泣き立てて空腹を訴えるから、母乳を与えなければならない。そのうちに「早うままにせんかい」大人まで空腹を訴えるので、授乳も半ばで急いで食事の準備をしなければならない。男達は満腹すると昼休み(昼寝)するが、嫁は食事の跡始末、夜飯(よめし)の準備、せんたく、幼児に腹一杯の授乳をしなければならなかった。この男達の昼休みは苗代頃から秋の取り入れ頃まで毎日続き、秋は昼休みは無く、さらに夜なべ(夜業)が加わった。家により年中夜なべをし、農閑期でも薄暗い囲炉辺でわら仕事に家族全員精出す家もあった。
しかし、このような農家の忙しい一日は、大正末期から昭和にかけての農具の改善などで作業形態も改まり、生活に余裕が出来るようになると男達は社会的活動面へ、女達は家事や育児に手をのばし、家計にもゆとりがでて農家の生活水準が少しずつ上昇するようになった。とくに戦後の農家の経営は、近代化にともない鼻作業は一段と進歩して生活は文化的、レジャー的になり、民主的な自由な思潮がかつての農奴的生活から人々を解放した。
二、衣類
衣類の自給 藩政の頃ほもちろん、明治の中頃になっても機(はた)を織る農家が相当多くあった。即ち、畑で栽培した麻や綿、蚕の繭糸を紡いで糸をつくり、それを機で織った。おもに農閑の冬季に女達の手で根気よく織られた。当時、わが国の繊維工業はまだ開発されず、ほとんど手織り工芸品の状況であったので、換金生産でない農家が衣類を購入することは至難であった。従って衣類は他の生活必需資材同様、自給自足するよりしかたがなかった。明治末期から大正になってようやく紡績工場や織物工場が設立され、一方で農家も換金副業的経営に移行するようになって、自給のための機織りも次第に農家から姿を消した。
短じり 「じり」は尻(しり)のことで膝下の意。即ち腰から下が短い着物のことである。が、今のミニスタイルと異なり、藩政の頃は短じりの作業衣が百姓の制服姿で、どんな場所でも短じりであった。「お茶にも、屋根ふきにも」のことわざのとおり実に簡素な姿であった。この短じりの服装は明治時代に入ってもすぐ改まらなかった。
男の場合は黒、または濃紺木綿のもじり(筒袖でしりがかくれる長さ)が上衣で、同じ生地のももひき(ヒザまでの長さ、付けひも、またボタンが無く重ね合わせ)を下にはく。もじりの腰には帯のような布ひもを締め、帽子のかわりに手ぬぐいのほおかむりや鉢巻き姿であった。雨の日には桧笠(ひのきがさ)にばんどり(みの)を着た。女は男と同じもじりが上衣であったが、明治頃から絣(かすり)模様が用いられ、だんだんに華やかな色模様に変わった。もじりの上に腰巻き(尺副、縦に四幅、ヒザまでの長さ。のちかすり物に変わる、もんぺの前身)を巻いた。これは男のももひきに相当するものであった。下着は男子では白木綿のふんどし(三尺ものはひも付き、後六尺ものも出来る。徴兵検査は三尺ものに定める)を締め、女子は現在のズロースやパンティに相当するしたいぼ(木綿二尺幅、横に二幅、付けひも、かすり物から赤色、のちネル地に変わる)を腰に巻いた。髪型は後頭部に束ねて結び、屋内でも常に手ぬぐいをあねさんかぶりに巻いていた。雨具は男同様だったが、のち、ばんどりのかわりに藺茣蓙(いござ)を二重に折り、横に背負うようになった。
これらの「短じり」の服装は農作業衣が本体であり、明治中頃までけ農作業に出る場合は使い果たした布継ぎのものも着たが、のちは織物工業が開発されるにともない、女物は色模様の美しいかすり柄が出来、友禅の小幅帯、色とりどりの飾りたすきなど、田植え頃水面に映った早乙女達の情緒豊かな景観は印象的であった。この姿は長く続き、昭和の戦時頃から男は洋服型の作業衣、女はモンペ姿に変わった。このモンペは作業衣として実用的で、戦後に至っても用いられている。また、「あねさんかぶり」の手ぬぐいも様々なデザインに変わり、雨具も笠や「ばんどり」は珍重な風俗文化財になってしまい、化学資材の便利なものが次々と流行するようになった。「もじり」「ももひき」も全く姿を消してしまい、新しい婦人作業衣が作業の近代化とともに登場している。
長じリ 短じりに対し、長じりは足くびまでの長い着物で、羽織は上衣に相当する。藩政の頃は役人や町人の服装であったが、明治、大正と農民生活に余裕が出来ると、男女とも作業時外は普段着となり、紋服まで着るようになった。また、男子の礼服として、はかまも着けるようになった。とくに衣類は女の生命とまでいわれ、衣裳持ちの欲望は際限なく広まった。農民も生活水準が上昇するにつれ、男女とも仕事の合い間に外出することも多くなり、長じり服装の需要が多くなった。
藩規制の絹物や色物、柄物も明治から自由になり、大正頃には毛織物も用いられた。また、和洋折衷様式も流行し、夏はアッパツパと称するワンピースのような簡単な服装も出来た。下着はじゅばんと称し、男女とも綿や綿ネル、絹物などを用い、木綿のシャツもももひきもメリヤスに変わり、冬の寒さにも平気な種々の防寒衣類が続々流行してきた。晴れ着の反物もいろいろな柄の織り、染めが出来てきた。とくに花嫁衣裳などは金銀のししゅうものなど実に豪華になった。
昭和の戦時中はぜいたく物はもちろん、一切の衣料品は切符制で統制されたが、戦後の復興にともない、衣裳は一段と多様化して男子はもっぱら洋装に一変、女子も中年以下は洋装が普段着になってしまい、和服は特別な席での衣裳になった。男子の礼装はモーニング姿が普通になった。花嫁衣裳も一生に一度の女の夢とばかり、貸し衣裳という業者が登場して際限なく豪華けんらんを競っている。
防寒外被 昔の百姓時代はボロ継ぎの古着を重ね、外出にはばんどりで防寒したが、綿作りが行われるようになってから綿入り衣類が用いられた。即ち、どうぶく、そでなしなどで、これらは短じりに重ねた。長じり着の防寒衣としてマント、トンビ、コートなどの毛織物が用いられたのは明治末期から大正の頃である。女子は外出防寒着にケット(毛布)を肩から掛けた。大正、昭和に至ると、男子ではラシャ織りのマントからトンビが流行し、女子ではみちゆき、コート、防寒コートと、次第に華美なものが流行するようになった。洋服の時代になるとオーバーに改まったが、それも色や柄、デザインなどに変化があり、女物は華美な流行を追うようになった。
子供の衣服 赤ん坊はうぶ着に包まれ、おしめ(おむつ)をかかされ(あてられ)、つぶら(いずみともいう)に押し込められ、暗い家の中で留守居して育った。昔は子供の着物も全部和服で、成長にともない一つ身、四つ身と寸法が変わった。さらにその中間にないぎ(縫い上げ)と称し、袖(そで)や身丈(みたけ)を短縮、仮り縫いして着せた。これらはつけひもが付けられ、帯の代わりに背中で結ばれていた。学校に出る頃になってもこの着物で、冬は綿入れのものにどうぶく(筒袖で綿入れの羽織)やそでなし(どうぶくの袖のないもの)を重ねて着せた。
大正の末期に改良服と称する外被が流行、男女とも細かい格子じまのコートのような学生服を着たのも懐しい思い出であろう。高等科以上の生徒になると、しまの木綿ばかまをつけた。女子は女学校に入ると学校に規定された色の長ばかまをつけ、ひもを横に結んでたらし、おさげ髪にリボンなどを飾り、中ヒールの革ぐつをはいた。時代の情趣ある風俗であった。昭和になると男の子は小学校から洋服に変わった。夏は霜ふりの裏なし、冬は黒のネル裏、つめえりの小倉服、女子は夏だけアッパッパと称するワンピースのような、裏無しの簡単な洋服が流行した。昭和十年頃から女の子も全面的に紫紺の水兵服に変わった。戦争中は女子は全部もんぺで、戦後正毛織りの上質な生地で、学校ごとの制服になった。高校卒業後は男女とも大人のような流行の服を着ている。
よぎと寝ござ これは昔の寝具で、よぎは夜着の意、現在のふとんのことである。大きな袖があり、たくさんの綿を入れた木綿の生地に、唐草模様など大きな表柄のものであった。元来このふとんはかなり文化的な生活をするようになった中世頃から用いられたものらしい。以前は着の身着のまま寝て、その上に別の衣類や布を掛けた。それが防寒の目的で発達したから袖がついているのであろう。さらに寒い季節は、かいまきと称する薄手の綿入れの着物をよぎの下に掛けた。このかいまきは後にケットと称する毛織りの真赤な毛布のようなものに変わった。この真赤な色はノミやシラミ、南京虫の予防になったらしい。敷きぶとんはくず綿入りの薄いもので、その上に藺茣蓙(いござ)を敷いたが、このござがのちに敷布に変わった。
大正、昭和になるとこのよぎも段々と少なくなり、軽い上質の綿と絹のふとん皮になった。戦後はエバーソフトのふかふかとした弾力のあるものや、上質の毛布、さらに電気毛布や電気敷き布などの暖房物が普及し、ますます過保護の生活様式に陥り、昔のたくましい生活が消えるようになった。
三、食べ物
米飯 農村でありながら、明治の中頃までは腹一杯にご飯が食べられなかった。一杯ままと称し、おわんに盛り切り一杯しか食べられず、あとは雑穀頬でどうにか満腹しなければならなかった。昔の農業は全く肉体労働ばかりで、現在の食欲で考えられないほど農民は大食だった。
雑穀はいっこ(いりこ、おちらし)やだご(だんご)が主で、現在の家畜や鶏の飼料以下であった。それほど農民の作るお米は貴重な存在で、例えば住宅建築などの工事で手伝い人を集める場合、賃金よりもまずお米を大量に準備しなければならなかった。
大正時代になると一杯ままも次第になくなり、白い飯が腹一杯食べられるようになった。しかし、お米は少しでも換金に当てたり、小作農は年貢米に出さねばならず、自家消費米と称する下等米が多かった。戦時下では供出米が優先的で、農民はまた白いままが十分食べられなくなった。戦後、米の生産過剰が一時的に悩みとなったが、将来もこのお米だけはわが国民の主食として貴重なことは決して変わらないであろう。
おかず 昔のおかず(副食)は大部分自給食で、野菜が主体であった。大正時代になって主食の一杯ままが次第に解消すると、おかずが問題になった。そのころはとくに動物性タンパク質が十分食べられなかった。例えば一匹のサバでも薄い輪切り一切れ、カレイも細い短冊型に切った一切れしか、皿に乗らず、その煮汁で野菜物を煮たのが大部分で、それがまた非常にうまかった。
その頃、本村へ相川の漁師が春になると砂つきの大羽イワシをざるに入れて売りに来た。そのイワシのわら火焼きの味は今になっても忘れられないほどうまかった。鮮魚のさしみなど大宴会でなければロに入らず、河北潟から年の暮れに売りに来る生きたフナなどもお正月でなければ食べられないごちそうだった。そろばんといってこま切れにしたフナに大根おろしをまぜたなますはうまい物だった。また、町へこやしとりに行った帰りに、魚屋からブリの頭を安く買って来てナタで割り、大根にかぶし(味つけ)て煮たのもよく食べた。鶏肉のかしわなどは婿様ちょうわいか重病人でないと食べられなかった。鶏を飼っている家もあったが、卵は自家用よりも親類などの病気見舞い品に流れ、時折り一個の生卵を数人でわけ、温いご飯にふりかけたのもうまかった。
昭和の頃になると漁業法の発達と輸送の便がよくなり、えんじょうもんと称する他県産のもの、とくに北海道産の割安な魚が豊富に入荷し、自転車やリヤカーに積んだ魚売りが多く来るようになった。また、牛肉や豚肉も事ある時にロにするようになった。戦時は主食すら満足に確保出来ず、野菜は自給出来たが、魚類は塩物を少々配給されただけであった。経済復興が進むにつれ、農村の生活水準は上昇してきたが、農業の兼業化傾向が進むと自給化が低下し農家でありながら野菜物まで購入するようになってしまった。そしてふるさとの味はふるさとで求められず、町のレストランのコマーシャル用語に変わってしまった。
子供のおやつ 戦前までは家の周囲にどの家にも柿、桃、杏(アンズ)、枇杷(ビワ)、ぐみ、粟、いちぢくなどが植えられていた。また、うりや(野菜畑)にはアマウリ、スイカ、カボチャなどが植えられ、四季を通じて果物の自給が出来た。各家々ではいりごめ、かきもち、かいもち(かゆもち、おはぎ) こねだご、そばなどをたびたびつくり、お互いに近所へも配り合い、常に農村独特のおやつがあった。
しかし毎日の子供のおやつは十分でなく、昔の子供達は畑のアマウリや堅ウリをこっそり取って食べたり、干し大根をかじったりした。秋にはもみがら焼きの中へイナゴを刺し入れ、赤く焼けたのも食べた。通学途中の部落に葬式があると、待ちこがれ、お供えの盛物やまんじゅうは先を争って受け取った。学校の弁当のおかずも連日梅干しとたくあんばかりで、アルミニュームの弁当箱のふたも梅干の酸ですぐ穴が出来てしまった。
発育盛りの少年期なのに栄養不足から体格が悪く、徴兵検査では五尺一寸五分(約一五六㌢)以下の不合格者がたくさんいた。女では五尺(一五二㌢)女郎(めろう)と称し、長身はかえって敬遠され勝ちであった。戦後、家の新築拡張で果樹は切り倒され、うりや作りの手間は出稼ぎやレジャーに流れ、かきもちより菓子やせんべい、かいもちよりケーキ、スイカやアマウリより清涼飲料と、親が与えたお金で好みのおやつが店頭で求められるようになった。子供達もおかあさんの味を知らない人間に成長し、生まれ育った故郷の懐かしい味が人の心から消えてきたことは実にさびしい。
酒、たばこ、茶 藩政の頃ほ百姓のし好、飲食は、規制よりも食べることに精一ぱいで、百姓の生活にはそんな余裕がなかった。明治時代になると農民生活に少しのゆとりが出来、種々のし好品も消費されるようになった。明治二十年頃、自家用濁酒製造が届け出によって許可され、写真のような鑑札が下付されていた。しかし、間もなく酒の製造販売は国の管理下になり、間接課税されるようになった。
たばこは古くから鶴来方面に栽培されていたが、本村でも自家用に少々畑の隅で作り、刻んで喫煙することが出来た。だが明治中期頃から専売制となった。
茶は随分昔から飲用されていたが、全く自給であり、畑の隅や田のあぜに植えられ、今もその古株が所々に見られる。これも明治末から大正時代になると分業化し、もっぱら購入品となった。古くから「お茶のみ話」「お茶のみ友達」「お茶も出さずに失礼した」など、農村社会交流上欠くことの出来ない存在であった。当時は上品な菓子などより、自家製のつけ物やいりごめ、かきもちなどを添えて供応されるのが楽しく、親しい同士がいろりを囲み、四方山の話をかわすのも当時の娯楽の一つであった。このお茶のみ話における個々家々の交流が、都会に見られぬ農村の人情や共同団結心を育んで来た。とくに平地の本村各部落は、農家が密集しており、部落内の交流に便利で、相互扶助の気風と一村一心の団結心もこのお茶のみ交流が発端ともいえる。
四、家財道具
神棚 藩政時代、キリスト教抑圧のため仏教を庶民にすすめる政策がとられた。本村も一向一揆にあらわれたように仏教王国の中心地であり、一向宗教義は百姓の内面生活に通ずるものがあった。明治になって朝廷と神ながらの道の結合から神道を高揚する施策として神社を国家管理にし、明治元年神仏分離令が発令された。そして伊勢の皇太神宮を本廟とし、全国津々浦々の神社に至るまで、その統制所管を行政機構に織り込んだ。その中でもとくに皇太神宮の神符である大麻を行政系統を通じて各戸々に配布し、これを祭らせるようにした。最初はこの大麻を床に飾ったり柱にはったりしていたが、次第に神社装備にならった小型の神棚を備えるようになった。そして家屋内装の充実とともに、各家々の仏壇のように豪華な装飾的調度品として、居間の一隅に高く飾られるようになった。終戦後、神社は宗教法人のように行政面から切り離し、従って大麻も神社法人系統を経て自由に受け、各戸に祭るようになった。
仏壇 各家々に仏壇が据えられるようになったのは藩政末期頃からで、文明年間頃(一四六九~一四八六) に蓮如上人直々の布教を受けた頃から、一向宗信徒が一般庶民の間に生まれて来た。当時の拝彿勤行ほ寺院や道場で行われた。その後信仰が深まるにつれ、寺の僧侶に乞うて南無阿弥陀仏の六字名号を書いてもらい、字は読めなくても、家の出居の奥に掲げて日夜拝んでいた。
六字名号は蓮如上人が吉崎御坊から四十万の善性寺への道中、粟田新保で休息の折りに筆を染められたものであると伝えられている。寛永から寛文年間(一六二四~一六七三)、檀家制度が確立された頃から、寺院や道場中心の勤行様式が次第に個々の門徒の家に移行するようになり、初めて在家の仏壇が備えられるようになった。藩の奢侈禁令下でありながら藩の信仰政策上、仏壇に限りきびしい取り締まりがなかったようである。
しかし、貧しい水のみ百姓には豪華な仏壇などおよばず、簡単な箱型のものしか備えることが出来なかった。明治時代になり、農民の財的余裕が次第に増大するにつれ、金ぱく張りの豪華な仏壇が据えられるようになった。とくに加賀美術として藩政時代から製箔(はく)、漆器、蒔絵、沈金、象眼のけんらんとした工芸品の発達は、金沢厨子(ずし)や美川厨子を生み、全国的にもその名声を誇るに至った。厨子が備え付けられるとともに、その本尊も本山から絵像、木像が志納によって授けられた。
この本導の阿弥陀如来像は本山から受けたものをほんもんと称し、裏書捺印があり、市販のものはばたさまと称した。昔から「お厨子ゃ貧乏すりゃ先に出、金ゃ溜りや後に入る」といわれて来たとおり、容易に求められるものではなかった。新たに厨子を求めて据えつけると、お坊さんを招き、村人も招待して、おわたましと称する祝いのご披露をした。そしてお坊さんの勤めの後、女や子供衆にはまんじゅうや果物を配り、男衆には坊さんを囲んで祝い酒をふるまった。この料理は仏事であるが、魚や肉物を使った。現在もこの慣例が残されているところもあるようだ。
家具調度品 藩政の頃の百姓はまず、衣食住の最低確保と、これに付随する生活必需用具確保が精一杯の生活水準であった。明治時代になって藩のきびしい生活規制が解かれ、農家の経済にも少しずつ余裕が生じるようになった頃一方、武士階級は禄高を失い、転業資金を得るため、彼らが所蔵していた家具、調度品、美術品などを換金しなければならなかった。これらはどれも皆、まずしいながらも百姓が常に胸に描いたあこがれの品々であっただろう。
少しの財力余裕が出来た農家へ、その頃急増した古道具屋と称する副業行商人がいろいろな品物を持ち回った。その主な調度品は、婚礼や仏事、祝宴用の朱塗り、黒塗りの各種御膳(ぜん)類、婚礼用酒器類、掛け軸、扁額(へんがく)、屏風(びょうぶ)、床置き物、火ばちなどの美術工芸品等であった。とくに金沢近郊の本村などは農産物の販売、こやしとり、婚姻縁故関係からその交流が深かったため、これらの調度品が多く入った。また、その頃から嫁入り道具も大正時代にかけて次第に華やかになり、米蔵兼用の道具蔵も建つようになった。昭和も戦後になると建築物の完備とともに室内装飾、調度品すべてが飛躍的に高度化し、近代的な中にもこれらの骨とう品が一層重宝な存在となっている。
魔除武具(まよけぶぐ) 一向一揆の火元である本村周辺では秀吉の刀狩りに続いて藩がきびしく庶民の武具、武器を取り締まった。このため埋もれた古い遺品や記録は農村にはほとんど発見されない。現在、各農家に魔除けとして遺されたのは、赤さびたぼろぼろの刀剣、槍(やり)、長刀などで、明治初期に藩の武家から古道具として買い入れたものである。
これらは古くからの俗信で、家中に魔の邪神が入り込むのを除ける意図であった。しかしその後、大戦争中の刀剣活用と凶器取り締まりによって減り、長刀などほその柄やほこ先の短いやり類だけがわずかに残されているに過ぎない。
五、普請
こわしまえ 普(あまね)く請う-即ち皆様方にお顧いするという意で、昔から農家で建物を建築する場合は、資金だけでは建たなかった。「死儀普請」といい、農村社会の相互扶助の二大重要事であった。この普請事は特殊な技術的労力や資材のほかは全部自給自足であった。
まず古い建物をこわす場合、各農家や親類が寄り集まって無報酬で手伝いした。顔も身体もすすとごみにまみれ、古材は他の用途を考えてていねいに扱った。専業農家はわずかで、種々の兼業農家や非農家が入りまじった現在の部落構成では、手伝い労力を求めるのも困難になった。また、古材利用はかえって手間になり、燃料の変革で用途はなく、その棄却にも苦慮しなければならない状態である。
地がち 昔はセメントなどが無かったので、建物の基礎は地がちをして固め、その上に石を並べて建物を建てた。だからこの地がちは非常に重要な工事であった。ケヤキの根株の短い丸太(直径五〇~六〇㌢)にかすがいを教十本打ち、それになわをタコの足のようにたくさん結んだものを使った。これはタコといい、数十人の人夫がそれぞれ気合いを合わせてなわを引っぱり、高く(一~二㍍)上げて一気に引き落とし、大きな石でも地中に打ち込んで固めた。気合いと調子を合わせることが大事なので、自然に生まれたのが地がち歌である。(付録俗謡参照)この音頭は非常にリズミカルで、人夫達もほどよく酒気が回り実に景気のよいものであった。
昭和時代になると業者請負い人夫で人数も少なくなり、高いやぐらに長い筒柱を立て、滑車で引き上げるずんどこ(長筒ともいう)を用い、地域外の人夫の職業的労働になってしまったので、和楽的情緒が少なくなった。その後コンクリート打ち基礎工事が簡単になると、地がち歌は人々のロからも消え失せてしまった。
手斧(ちょんの)始め 昔は製材機が完備されていなかったので、大工は丸太を手斧(ておの、ちょんの)で削って角材にした。大工作業はまずこの手斧を使う木造りから工事に取りかかった。この初日に祝い酒が出された。翌日から大工は毎日建築現場で働いた。昼飯のほか午前、午後の二回の休憩時に、たばこと称するお茶と間食が毎日出される。当時はみな自給の食べ物であったから、毎日同じ物を出すのもどうかと女達の工面も大変だった。が、その間、親類で時折り大工見舞と称し、かいもち(おはぎ)、まんじゅうなどを贈ってくれたので大助かりであった。明治中期以前では人夫賃金よりも食べ物がより重視され、当時は普請するには建築資材とともに飯米を十分準備しなければならなかった。
たちまえ(たてまえ) 昔の自給自足の普請では、部落や親類の相互扶助の手伝いのほかに、用材の手伝いも行われた。各農家が宅地内の手頃な立木を、一本あて持ち寄ったのも大助かりであった。普請中最大の祝いごとは、大工の木造りも終わり、いよいよ建築にかかる日が最高であった。部落内はもちろん、遠い親類まで大勢の人々が祝い酒をたずさえて朝から手伝いに集まった。
近い親類は赤飯やみたま(小豆のかわりに黒豆をまぜてむし上げたもの)、モチなどの祝いの品々を贈り、大勢の手伝いで次々と組み立てられた。カーン、カーンというかけやの音、ヨイショ、ヨイショと太い棟木がロープで引かれる景気のよい掛け声が、遠く夕陽の彼方まで響いて、まず無事でめでたし、めでたしの笑顔が一様に新築家の棟に注がれる。この時、大黒柱には南無阿弥陀仏のはり紙や数珠が掛けられたりサバがつるされたりする。これは新築家に天狗さんが住み込むから天狗さんの最もきらいな仏事やサバを表示するとよいというこの地域の俗信である。また壁土を踏む仕事は若い嫁さん達にさせると、美しく塗られた壁になるということだった。多分、若い女のすそを巻き上げた素足の曲線美にかこつけた、男衆の一興から発した説であろう。日も暮れる頃、他家の出居(座敷=でい)を借りて祝宴が設けられる。大工を上座に手伝いの人々が居並び、にぎやかな酒宴が夜中まで続く。この祝い酒も時代が進むにつれ折詰や大ダイ、赤飯やみたま、まんじゅうの手土産が大風呂敷に包まれ、だんだん豪華になった。
たちまえの手伝いは現在、レッカーなど機械力が登場して、勇壮で景気よい掛け声も開かれなくなり、工事も手伝い人夫でなく請け負い方式となって、祝宴だけがにぎやかになってしまった。
なお、このたちまえは三りんぼうの日を避けることが迷信的に堅い通念とされている。翌日からさらに屋根や壁、部屋の内装と工事が続くが、昔は全く村人や親類の手伝いで出来上がった。現在はすべて金銭で家が思うように出来上がる時代に変わった。
間取りと様式 明治初期はまだ藩政時代の家造り規制による規模様式だったが、次第に下屋などをとり付けて拡張され、わらぷき屋根でも両づの屋根、片づの屋根が出来できた。明治末期から大正時代には武家屋形にならったかわらぶき、やかた造りの大規模な農家や、かわらぶき下屋による増築も行われた。従って間どりも出居が土縁付き書院造りの座敷になり、かぎの間も縁付きの奥座敷になった。床は明治時代から畳の間がとり入れられた。
座敷は仏壇が飾られているので仏事使用が多く、天井板張り、床付き、帯戸、唐紙張りふすま、長押(なげし)、欄間と、年々内装が整ってきた。また、大正末期から昭和にかけてはガラス窓も取り入れられ、電灯のとり付けとともに一層明るい住まいに改善された。
昭和に入ると本居で炊事をすると家屋内が汚れるので、別棟や下屋根付きのひどこ(火所)が造られ、一方で広い本居の一隅の食事場を仕切って食堂としたり、下流し(昔の台所の水所)を改造して箱型の高流し台を備えたりした。また、玄関口のにわでの作業は、発動機やモートルなど農業機械導入によって、ちりやごみが飛散するので、別棟の秋納屋と称する作業場が次々と新築された。穀物ばかりでなく種々の調度品も数多くなったので、明治末期頃、所々に土蔵が造られた。中には白壁の装飾をしたものやネズミの被害を防ぐために石蔵に改造されるものも多かった。
このように大正、昭和時代は明治時代に比較して、農家の衣食住ともども生活水準は飛躍的に高まっていった。戦時中は一時停滞していたが、戦後の昭和三十年頃から本村の建築ブームが始まり、全く部落のたたずまいを変容させてしまった。そして外観はかりでなく、内装から調度品に至るまで、目を見はるように高級化が続き、さらに造園が後を追うように進められている。
六、光熱
火熱、電熱 食生活上不可欠の火は、その発火用具が昔は火打ち石と火打ち金だったので容易でなかった。だから火種は毎日絶やすことが出来ず、夜寝る時、いろりの真ん中にもみ殻と堅木の木片を埋め、その上に火生石(ひけしな)という平らな石をのせ、その上に火ばしを交差して置いた。また、たくまいのたくもんば(薪置場)に引火するのを防ぐために、たくまいむしろをかけて置いた。翌朝一番先に起きた嫁は、この埋ずみ火の火種で火をおこし、ご飯やおかずを炊いた。ぼんやりしていて火種を切らすと大変、箱(マスを用いた)に灰を入れて隣へ火種をもらいに行かなければならない。たびたび続くと「間ぬけな嫁」として姑の茶話の好材料になった。
明治中頃、つけ木と称する長さ十㌢に幅五㌢ほどの薄い板の先に、硫黄を塗ったものが使われた。これは縦に細く割って火種につけると、燃えた硫黄から板に移り、たき木に火がつけられた。マッチが出来たのはそのあとで、はやつけんと呼ばれたのは早いつけ木の意である。これで種火の用はなくなり大助かりだった。当村は平地で山林はなくたき木はほとんど使われず、燃料はわらが主であった。
昭和中期にかかまど(もみ殻かまど)が一時普及した。これは特殊構造のかまどへもみ殻を詰め込み、少しずつ自動的に燃えるもので、火力も強く、手間もかからず、わらの節約も出来て便利であったが、すすで室内が汚れたので困った。その頃本居のいろりで煮たきすると煙で困るので、ひどこと称する別室が造られた。このひどこは台所兼食堂のようなものであった。
戦後農村の住宅は全面的に改造され、昭和四十年前後から台所の飛躍的な改善が普及し、ステンレス流し台にプロパンガス燃料のコンロ台、電気がま、瞬間湯わかし、トースターなど、全く煙の出ない台所になった。風呂だけはたき木を使ったが、間もなく電気温水器が流行し煙突の姿も消えてしまった。また、暖房用火ばちは石油ストーブに、炭火こたつは電気こたつに、湯タンポやあんかは電気あんかや電気毛布などに変わり、ついに冬の必要品の木炭もほとんど見られなくなった。
照明具は菜種油を使った行灯(あんどん)が明治の中頃まで続き、その後石油ランプが普及した。このランプは海外から輸入されたもので、最初はホヤの無いハダカ火だったため風が入るとすぐ消え、夏は困ったらしい。それでも行灯よりよほど明るく喜ばれた。
明治末期頃からホヤ付きで調節可能の二分しんランプが出回り、その型も大小、台ランプ(電気スタンドのような)、つりランプなど非常に便利になった。このランプのホヤは毎日掃除が必要で、子供達の受け持ち作業だったが、遊んでいて忘れると晩方によくしかられた。
ランプは約三十年余使用されたが、大正十年十二月(粟田・太平寺区は先に架設された)電灯が導入されて姿を消した。この電灯誘致は当時として相当難問題であった。個々の施設と異なり、共同架線工事によらなければならず、架線計画と工事費負担関係が部落間の利害をともない、村一円の共同工事として数回の協議が重ねられた。その工事費についての記録の一端を次に掲げよう。
富奥村電灯供給工事収支決算書
収入の部一、金一千六百九十三円三銭也
内訳一、金八十円也 矢作区 一、金四十八円也 藤平田新区 一、金二百六十四円也 上林区
一、金百二円也 清金区 一、金三十円也 位川区 一、金九十六円也 三納区 一、金三十六円也 藤平田区 一、金二百五十八円也 下林区 一、金百七円九十八銭也 上新庄区 一、金九十円也 下新庄
区 一、金二百四十円六銭也 末松区 一、金六十円也 役場
(雑収入省略)
支出の部 (省略)
大正十一年八月三日
工事委員 北村作次郎 谷市三郎 北川清次郎 宮川善太郎(小林千太郎代人)
以上工事費の分担割はいちおう決定されたが、送電維持にともなう毎月徴収の電気料金額は、電力会社の営利に関係するので、最小限の需要契約が必要であった。各部落ごとにその約定書が作られたが、次に一例として清金区の約定書を示す。
電灯約定書
今般富奥村字清金区ニ於テ富奥村ヨリ電灯配当数十燭八十五個此料金一ヶ月金四十六円七十五銭ヲ以テ最小限度トシ使用スルコトヲ約定致シ候而テ別紙ノ通り個人引受ノ責任灯数ハ点火ノ日ヨリ満四ヵ年間約定ノ料金ヨリ減少スベキ電灯ヲ使用致ス間敷候万一之ヨリ減少スル事アル時ハ右期間内ノ料金ハ一時ニ前納スべク若シ之ガ料金前納ノ履行ヲ相滞シタルトキハ料金ニ対スリ該当者所有ノ動産及不動産ノ差押へ処分ヲ受クルそ聊モ異議不申候仇而後日ノ為約定書一札如件
大正拾弐年給弐月廿六日 各人連名署名(捺印)
清金区責任電灯料引受人総代
宮崎庄次郎殿
次に各個別の電灯数が約定されているが、家により六個から二個の差があった。
総工事費一千七百円(粟田新保・太平寺ほか)その他毎月の電灯料金の負担が新たに加わり、米価石三十円以下の当時としてたしかに容易でなかったであろう。しかし、従来のランプの照明と異なり、屋内はもちろん、部落内の路面まで明るくなって、農家の夜なべ仕事や子供達の勉強に至るまで便利になった。その喜びは当時物心づいていた人のだれもが記憶に残っていることであろう。昭和十年頃になると農作業電化の初めとして単相モーターが使用され、電球も燭からワットと明るく改良され、蛍光灯も開発されて照明度が高くなった。
戦後、農家の住宅新改築にともない、屋内の壁や天井裏に自由に配線して家庭電化はラジオ、テレビ、ステレオ、せんたく機、冷蔵庫、掃除機、炊飯器、ミキサー、トースターなど際限なく広がる一方、農家の広い応接室には豪華なシャンデリヤが輝き、電気の需要増加は文化生活のバロメーターとなっている。
七、衛生
飲料水 各農家の台所の外側に必ず小川が流れており、その小川を「のみすか」と呼んでいた。「のむ水川」の意で、昔ほ用水を汲んで飲料にしていた。その時代はこの小川も山間峡谷の泉のように汚染されない清水であったのだろう。地下水を汲み上げる掘り抜き井戸は、藩政時代にはすでにあったようだが、本村など地下水位が二十五㍍前後の低い所では、各家ごとに掘るのは困難であり、各部落共同の井戸がわずかの数しかなかった。(太平寺は割合浅く十㍍位である)
この共同井戸のつるべなわは、わらなわを九本よって造ったもので、つるべを二個両端につけ、滑車をとおして引き上げた。手おけ二個を天びん棒でかついで運ぶのは、非常な労力と時間をともなった。昭和の初め頃「のみすか」の水を引いてろ過するすまし井戸装置をした家も相当あった。上林の部落が共同で大規模の浄水池を構築、各家に配管したのが昭和七年であった。戦後、昭和二十六~七年頃に従来の井戸水をモーターポンプで吸い上げ、タンクに貯え各家に配管する簡易水道が県費補助を得て各部落一斉に設置された。保健所から水質検査の指導を受け、良い水をやすやすと台所に引くことが出来て便利になった。現在の当村の飲料水は全部簡易水道を利用している。
風呂 明治前の貧しい農村では家ごとに風呂の設備があったわけでなく、なべで湯をわかして大きなたらいで行水のように身体を洗い流した。高持ちの大百姓でも粗末な鋳物の底がついたおけをかまどに伏せてわかす地獄風呂があった。このおけ風呂は明治から一般に使用し、終戦以後もなお続いて使用した。
経済復興で各農家が家を新築するようになってから、鉄のかま風呂にかわってタイル張りの便利な風呂場が造られ最近では重油バーナーや電熱温水器やシャワーが整備され、浴槽も合成樹脂の美しいもので、内部設備の整った浴室が全農家に出来るようになった。
「しょんベんちゃ」と「かんしょ」 昔はかんしょ(大便所)としょんべんちゃ(小便所)が別に分けて設けられた。しょんべんちゃは玄関わきにあり、おけを置いたものや、そのおけを地中に埋めたものである。にわとの境は小さな開き戸や、こもをたれ下げた簡単なもので、男女とも使用した。かんしょはこやし納屋の一角にあって、大きなおけを地中に埋め、その上に三十㌢幅の厚板二枚を渡し、両方の板をまたいでかがみ、天井からたらしたなわを振って用を足した。しりぬぐいも紙などを使わず、わらすべを打って軟かくしたものが箱に入れられていた。囲いもこもをぶら下げた簡単なものであった。家からはき物をはいて、雨天でも離れた納屋まで行かねばならず、子供などは落ちることもあって非常に不便だった。
明治の頃に、かぎのまの奥に、おくがんしょが出来たが、家族の使用すべきものではなく、来賓客分の僧や婿の大小便所として使用された。幼児用にはだ円形のおけを、にわの隅に置いた。「おまるこ」と称するのは今と同様だった。
昭和になってかんしょがしょんべんちゃの横に設けられ、同時にしりふきも紙くずに改められた。また、陶器の便器も用いられるようになった。戦後はタイル張りの美しいのに造られ、水洗便所も普及している。
昔から大事な自給肥料として使った糞尿も、汲みとり料金を支払って衛生社に委託するようになった。
とやまの薬 いつからかわからないが、富山の薬売りが大きなつづらを重ねた荷を背負い、越中弁で愛想良く、夏の盆前と正月前の二回まわってきた。どこの家にも四袋か五袋置いてあった。昔はよほど重病でなければ医者にかからなかったので、たいていの病気はとやまの薬に頼った。大部分が漢方薬で、実によく効いたものであった。「六神丸」「感応丸」「安神丸」「仁丹」くだり止めの「赤玉」「熊胆(クマの胃)」「歯痛止め」「風邪引きトソプク」「反魂丹」「頭痛膏」「あかぎれ膏」など、家庭薬として実に昔は重宝な存在であった。景品に広告入りの紙風船や、食い合わせ中毒図など置いて回ったものである。また、洋服姿で手風琴を鳴らし、「オイチニ、オイチニ」と軍歌など調子よいメロディで歩く薬売りもよく来て、子供達がその後にゾロゾロついて歩いた。そのほか、なじみの薬行商人が回って来た。「ねりやく」「混元丹」などは農繁期前や病気上がりの時など買った。医療に便になった現在でもやはり「とやまの薬」は回って来る。家庭薬の種類も化学剤が多くなったようで、軽い病状や外傷など便利である。
はり灸(きゅう)とやけど 昔は簡単なはり灸療法が多く用いられた。平木の灸、ばんばの灸(粟田新保)そのほか随分遠い所まで、不便な道を根気よく通う人もあった。やけどしたときは所々に家伝の漢方薬による治療法があったので通った。そのほかまじないや祈祷などもあった。このような神がかりの療法はあまり重視しなかったが、衛生知識の低い昔はこの療法にすがった人もあったらしい。
藩政の頃はもちろん、百姓対象の医師は無く、明治初年の皇国地誌に依ると粟田新保村の民業一覧に「医ヲ業トスルモノ一戸」と記録されているのが、おそらく本村内医療所の初めであろう。戦後は富奥村立の診療所が新設され、以後本村民の健康と医療面に大貢献している。本村が伝染病大流行で困ったのは、明治二十年頃のコレラであった。当時の村民はコロリ病と称し、伝染病の病理を解しないのと医療機関の不備な時代であって、死者が続出し、各部落の火葬場に煙が絶えない状態であった、と古老は語っている。十戸ほどのある部落の火葬場に一時に二個の土箱が並び火葬に困惑したそうである。その直後、中林に村立の伝染病隔離病棟が建てられた。農村でこのような施設が出来たのは、当時としてほ他に類のないことであったそうだ。その後肺結核の流行で、本村でも一家が全滅しようとした家もあった。明治四十五年松任町ほか十二力村伝染病予防組合がようやく設立された。戦後は国、県の施策として種々の方途が強力に施行され、国民健康保険制度も実施されて医学、医術の躍進とともに診療所を中心とした本村の医療体制が整った。
明治四十五年設立の伝染病予防組合
組合名称
松任町外十二ヵ村伝染病予防組合(参加町村)松任町、柏野、宮保、一木、出城、安原、郷、中奥、林中、山島、舘畑、旭、富奥村 議員数 二七名 組合戸数 五、一五三戸
この予防組合は事業として松任町に伝染病院を設立したるを初めとし、云々 (石川郡誌)
大正末期伝染病患者数 (石川郡)
病名 大正十年 大正十一年 大正十二年 大正十三年 大正十四年
患者 死亡 患者 死亡 患者 死亡 患者 死亡 患者 死亡
赤 痢 二人 二人 三人 一人 一人 三人 二人
腸チフス 四三 七 八二 二〇 二三 五 九 二 一二 三
バラチフス 九 六 二 一 一 二 四
ヂフテリア 四 二 五 一
合 計 五八 七 九〇 二二 二九 七 一二 二 二四 六
石川郡内衛生関係業者調査表 大正十三年調べ
医師五二、歯科医師一一、薬剤師一〇、産婆五七、看護婦二〇、鍼灸術一二、按摩二六、薬種商三六
[part1] part2へ >>