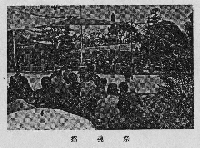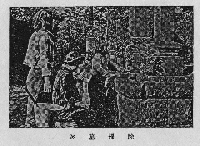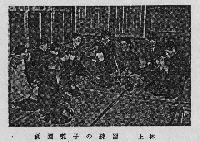<< part3へ [part4]
==第四節 年中行事==
第四節 年中行事
人間の生活はその環境によく影響されるが、その地域的環境を同じくし、その時代的社会制約の下に生きる個々の村人の間には、自然と普遍的な風俗風習がかもし出される。それが通例化し、行動的に四季折り折りに生まれたのが年中行事であろう。
山もなく、海浜にほど遠い平坦な水田に囲まれ、点々と散在する集落に生き、めぐり移る四季を甘受しながら、農の道一すじに培って来た本村にも、やはり農作業を中心とした情緒豊かな年中行事があった。しかし、世相の変遷につれ、それがだんだんなくなる傾向にあるのはさびしいことである。今はなつかしい明治、大正の頃の年中行事について、四季を追って思い返してみよう。
一、元旦
大晦日の夜ふかしで疲れていたが、東の空が白々する頃は皆起きた。元日の朝から寝坊すると、一年中寝坊するようになるという教えは、子供心にもよく分別していた。子供達の朝一番の役目は若水汲みであった。飲料水はその頃はもう共同井戸の汲み水であったが、洗顔などの手水は外流し(引いてあるのみずか=飲水川=井戸のない昔は川水を飲料水とした)から汲んだ。小だらい(小さいおけの洗面器)で顔を洗っていると、いろりにかけた茶がまの湯がわきたって、ふたがガチャガチャ鳴っている。その昔でお正月の朝のふん囲気が感じられた。その音を背後に聞きながら、出居(座敷)のお厨子の前に座り、仏様にお参りしたり、神だなを拝む。日頃あまり素直でない子供達まで、正月の朝はなんだか心が浮き浮きして賢くなるような善行意識が沸いてくる。いろりの回りに家族が集まって福豆汲み(沸とうする茶がまに黒豆を数粒入れ、それを汲み当てた者は幸福になるという)をする。福豆が汲めないでがっかりする者、汲み当てて得々としている者、自然と笑いが出る。その間に大きな鉄なべの中の雑煮モチがやわらかく煮えると、それぞれ行儀よくお膳の前に座る。お膳の中には一年間まめまめしく働く縁起で黒豆の煮付け、何事にも数多く取るようにとニシソかずのこ、松前ダラとゴボウの煮付け、焼きブナとこんにゃくの煮付け、ハべン(かまぼこ)、ハヤビス(ところてん)みかんの三品盛り付け、大根のニシンこうじづけなど、非常においしい正月のお節料理が並んでいた。
ごきげんな子供はニコニコ顔で学校の新年拝賀式に参列した。先生も生徒も来賓も相応の礼装で、来賓は村長はじめ村の公職者が三十~四十名も並んだ。式が終わると子供達は祝の焼き印が入った紅白のまんじゅう(後に一月一日の文字を表わした紅白の落雁=らくがん)をもらって、喜んで帰った。元日は大人の間では外出をしない風習がありいろりを囲んだり、寝正月と称し日頃の疲れを休めたが、子供達は元気に遊び回った。
二、二日の仕事初め
農家では農作業が最も重んじられており、新しい年の初仕事としてこの日は朝暗い中に起き出て、どの家もなわの原料のわら打ちをする。寒いが、きねを振り上げると暖かくなって、肌着一枚で頑張る。そのきねの音が部落内に響いて、互いに今年一年がんばろうと誓い合っているように聞こえる。一汗流した後の雑煮モチの味はまた格別であった。
この日は朝前仕事で打ち切り、朝飯後は年始回りに出かける。日頃世話になっている家々、娘の嫁入り先など、まず一番に主人が出かける。女達は親しい家など回って、お茶飲み話の花を咲かせる。子供達は一生懸命書初めのけいこ。翌三日も部落内の年始回りやお茶飲み回りで過ごす。これが部落の共同生活で重要な心の結び合いであり、また唯一の娯楽でもあった。
こうした部落内の交流は心のつながりばかりでなく、出された自給の簡単な野菜料理やつけ物を食べ合い、研究懇談を重ねることにより、ふるさとの味、お母さんの味を伝えることに結びついた。これでお正月も終わったわけで日常何の娯楽もなかった昔の人々は、公休日としてのお正月を楽しく過ごしたのであった。「一日ゃついたち、二日ふっとたち、三日みるまにたった」といって名残りを惜んだ。四日からは平日のように農閑期ながら副業のわら仕事などに夜まで働いた。
三、七日正月
なにかぶと称し、一月七日は一日休日であった。この日は鏡モチを集めて小豆のぜんざいにして食べた。仏前の供えモチもあるので、精進物のぜんざいにしたのであろう。この頃になると、毎日のように乞食が続々玄関に立って情を乞う。社会福祉の施策が貧弱なこの頃では、実に乞食生活者が多かった。各家々では年暮れのモチつきの時に、特別乞食だんごというのを一うすついて準備してあった。こたつから寒い玄関までたびたび往復するのは、たいてい子供達の受け持ちであった。この乞食にも様々の部類があり、哀調で生活の苦しみを訴えて同情を求める者、下手な芸人のまね事で一曲、一節、一語りする者、サル回しがあり、お稲荷さん、福俵など年の始めから縁起のよいめでたい祝い文句を並べてくるものもあった。主人の背に負われて、物見高い村の子供達がぞろぞろ後からついて来るのを振り返って眺めている小猿の表情など、今は見られない情緒豊かな光景であった。そしてどこの親達も異口同音に「親のいうことをきかん怠け者は、大人になるとあんな乞食になるがやぞ」と子供をさとした。
四、左義長
十四日に子供達は学校へ提出した書初めを審査してもらい、放課後急いで持ち帰ると、左義長の準備をする。まず村の年長者がその年の暦を見てわざわいのない方向を定め、子供達は家々を回り、お正月の〆なわや松花、わらや青竹を集める。元気な青年連がそれらを高く積み上げて日暮れを待つ。薄暗くなると火がつけられ、子供達仕手に手に書初めを笹竹(ささだけ)につけ、それを風になびかせて寄ってくる。その書初めを火炎に当てると空へ舞い上がる。高いほどその子は上達するというので皆が見守る。高く上がると一斉に「ワァーッ」と歓声が上がる。火力が強まって太い孟宗竹(もうそうちく)が大きな爆音とともに割れると左義長も最高調。炎に火照った子供のまっかな笑顔と歓声が続く。八分どおり燃えると今度はふところから角切りのモチを出して、親も子も焼き始める。この火で焼いたモチを食べると、年中無病息災であるということである。帰る時、青竹の燃え残りを一本ずつ持ち帰り、いろりで小豆を煮た。
五、成り木のまじない
十五日朝、昨夜煮た小豆でぜんざいを作って食べる。そして、その余り汁をおわんに入れて持つ者、ナタを持つ者が家の回りに植えてある実の成る果樹の下に集まる。ナタを持った長男が大音声で「成るか、成らぬか、ずりこかせ(返答せよ)」といってナタでその木に斜めに切り口をつけると、他の者が声をそろえて「成ります、成ります、千成ります」と答え、おわんの汁を切り口に注ぐ。これは果樹が今年も沢山成るようにというまじないであった。
六、二十日正月
大黒柱にかけられた「きねまき」をおろして、乾いた割れ目から細かく砕いて、煮たり焼いたりして食べた。また「まゆ玉」もおろして処分し、これで一切正月の行事を終えた。
七、ちょうわい
二月一日から三日または四日間、「ちょうわい休み」といって仕事を休んだ。このときはまず娘たちが婚家から孫達を引きつれ、里へ帰って休養した。「ちょうわいモチ」やいろいろのごちそうをして歓待した休みであった。またこの間に「むこさまちょうわい」といって、嫁いだ娘の嫁を招待して接待した。封建制の名残りであろうか。この婿を迎えるのは大変なもので、大掃除をするやら、家の家具やごちそうなど非常な配慮をした。もちろん、婿は幾日も滞在したわけでなく、引かれるままに酔い伏して一泊、翌朝帰った。幾日も泊まった婿は「だらァーナあんさま」と世間の人から茶話の材料として笑われた。
またこの「ちょうわい」時には、常日ごろお参りに来てもらう近くの寺のお坊さんを招いてお魚料理で接待し、村人も呼んで「お参りごと」も催した。
元来このちようわいというのは、年の始めの休日に新嫁が姑の下でゆっくり休養するのが気がねだったので、親に年頭あいさつという名目で顔見たや見せたやで「ちょうわい」が出来たらしい。のちに暦が新暦に変わったため、正月だけ一カ月早くなり「ちょうわい」が二月になった。最近は子供の学校関係で「ちょうわい」も一月のお正月になった家が多いようだ。このように「ちょうわい」が重視された昔は、農家業の仕事が重労働できびしかったのと、食生活が常にみたされていなかったためと考えられる。今も残る「ちょうわい腹七日」という風刺や、次のような「婿様もょうわい」のカニ料理の笑い話などからうかがわれる。
「婿様ちょうわい」に招かれたある婿さん、ごちそうのご膳がでたので、よく見ると食べたこともないカニ料理。「こりゃ珍しい」とカニの甲だけはよけてかみついた。そばでお酌していた主人が「アッお婿様、そりゃいかん。ふんどし(カニの甲の中にあるエヲのようなもので食べられないもの)をはずしてお上がり下さい」といったら、お婿さんは立ち上がって自分のふんどしを取りはずして座り、また、カニにかじりついた。ご膳のわきに置いてあるふんどしはともかく、男性のシンボルが見えたとか見えなかったとか、お茶話の語り草である。
八、お彼岸
三月二十一日の中日前後の七日をお彼岸さまと唱え、主に仏事行事であった。即ち仏壇の掃除や手入れをし、彼岸だんご(後には落雁=らくがん)を供え、中日は休業する。七日間は下林や粟田のお寺でお参りがあり、ありがたいお説教があるので、年寄達は誘い合わせて続けてお参りした。
九、春祭り
三月中、各部落の氏神様を中心に行われた。秋祭りのようににぎやかではなかったが、各家々では赤飯やごちそうをして二~三日休業した。神社ではおごそかに祈年祭の神事が行われた。この休みはその年の豊作を祈るとともに、その年の作りの出発点でもあり、いわゆる農閑期から農繁期に移るポイントであった。昔は各部落ごとに期日の定めがあったが、明治中期に富奥村が誕生してから、村一円三月二十日前後の三日間と定められた。しかし、終戦後は一定していない。
十、井掘り
積もった雪もとけ、お彼岸を過ぎると、うららかな日よりが続いて枯れ草の間から「ヨメナ」「ヨモギ」「フキノトウ」がのぞき出す。いよいよ田作りが始まる。
まず最初に井掘りがどの部落でも始められる。かんがい用水の小川が砂や枯れ草で埋まったり、曲がったりしているので、かんがい前に整備するわけで、毎年欠かせない行事である。
この頃は用水も停水されるので、各部落ごとに共同で老いも若きも男女一斉に出てクワや「ふんずき」(近年は剣ずこ=ショベル)を使いながら精出して働く。共同で働く場合はとかく「だれだれはこまめによく働く」などうわさの種になりやすい。とくに新参の花嫁などは評価され勝ちなのでさらに心労も加わるわけである。午前と午後の二回「たばこ」と称する小休憩がある。この時には菓子類やパン、清涼飲料などが出され、腹をかかえるようなじょう談話の花が咲く。家で遊んでいた子供達はいち早くかぎつけて、母親のヒザにある物をねだりに来る。親はねだりに来るのを待って、自分は控えめに残しておくのである。
井掘り人夫はどこの部落でも二~三日間続く。冬の農閑期はこたつや針仕事、軽いわら仕事で体がナマっているので、急にクワ仕事で精出すと手足や腰が痛み出すことが多い。部落によっては井掘り休みを一斉にするところもある。しかし、もうそんなにのん気にしていられない。畦(あぜ)切り、苗代(最近はハウス育苗になる)作り、荒起こし準備などの農作業が待っている。
十一、草祭り
四月上旬頃、紫雲英の繁茂に感謝しながら一層の生育を祈念して、仕事を休む日を設けたのがその始まりである。紫雲英を肥料として用いたのは藩政末期で、識者の伝えによると慶応年間(一八六五~一八六八)に岐阜から石川郡へ来ていた行商人がその種子を伝えたという。当時はもちろん化学肥料は夢にも考えられず、また、満洲から大豆かすが輸入されてもおらず、魚肥や油かすは高価なうえ人糞尿も自給限度があり、紫雲英の出現は全く「地獄で仏」のようにありがたい存在であった。はじめは感謝の祭であったが、時を経るにつれてその心が消え失せ、休み日だけ慣例となって昭和の代まで続いた。現在は全く根絶し、その名も草も知らない人が多い。
十二、節供(節句)
四月三日、新暦では三月三日である。昔は武士階級以上の年中行事であって、百姓などには関係しないことであったが、明治以後は百姓にも精神的経済的余裕が出来、あこがれの形式を取り入れたものであろうか。ひな壇は飾られないが、お供えの草モチだけは作り、おひな様に供えず、娘の嫁入り先や孫達に届ける風習が自然に出来た。この草モチは昔は草だんごであったのがモチになり、草は色になって紅白緑三色の菱モチになった。最近では豪華なひな増がどこの家にも飾られるようになったが、お供えはあやしげなインスタントに変容してしまった。
十三、蓮如さん
四月二十五日は蓮如忌である。一向一揆の中心となった石川郡の中央にあり、蓮如上人が直接布教行脚したゆかりの善性寺(隣村四十万)でのお参りには、善男善女がうちつれて参詣した。交通が開けたこの頃は、吉崎御坊、二俣の本泉寺へも行楽を兼ねて参る人が少なくない。農作業面からいうとこの頃は荒起こしの最中である。人も耕馬も疲れ切っている。とくに借馬などは子供心にも哀れに見えるほど、お尻の骨が突き出すまでに瘠せていた。だからこの日は人馬ともども一日の休養をとったわけで年寄の説によると「蓮如様のおあたえ」とまでいわれていた。
十四、さつき休み
五月中旬、農作業中でも大事な田植えが無事終わったところでとるヒザ休めの日である。「小豆かいモチ」「黄粉かいモチ」を作って、田植えを手伝ってもらった家や娘の婚家へ持って行った。また、この日は田植え人夫の賃金精算をする日でもあった。
十五、雨やしこ
これもみな農作業にちなんだ行事である。田植え後の若苗はひと雨ごとに肥料を施したように良く伸び育つ。このため間をおいては訪れる五月雨は百姓に歓迎された。昔の農作業は全く機械力が無く肉体労働だけ。だから適当に休む必要があったわけである。「やしこ」の「やし」休養の意味「こ」は日時の愛称語である。「雨やしこ」や「草祭り」などの休養日は、個々の農家が定めたのでなく、昔の肝煎やのもの部落区長が農民の意を汲んで決定し、朝食前に「休み太鼓」を打ち鳴らし、あるいは「小走」がふれ回った。このようなことが農村社会の「ともに楽しみ」「ともに悲しむ」という共存共栄の考え方を生みだしたのであろう。
十六、五月田休み
六月上中旬頃になると二毛作の麦田、菜種田、紫雲英の種田などの収穫が行われ、続いてすぐ晩生苗の田植えが行われる。この田植えが無事終わると、さつき休みと同様に五月田休みがあった。この五月田休みは旧暦の五月に当たり、新暦では六月に相当するわけである。昔の稲は全部晩生であり、普通の田植えは五月(新暦の六月)であったので、田植え季をさつきと称したらしい。
十七、しようぶ湯
六月五日、それは旧暦の端午の節句である。この日は菖蒲(ショウブ)を沢山準備し、まず風呂をわかし、その中にショウブ、ヨモギなどを入れてはいる。寝る時は敷ぶとんの下や枕の下へショウブを入れて寝る。翌朝、そのショウブを頭に巻いて起きてくる風習があった。これはヘビにかまれないとか、ヘビが入ってこないとかの伝説から起こった習慣であった。この伝説も種々あるが、要約すると次のようである。
昔々かわいらしい娘がいた。その娘の寝所へ毎夜、実に美しい立派な男がしのんできた。どこの男か娘は不思議でならない。そこで娘は考えて、ショウブを細くさいて長く結んだ糸の端を、男の着物のすそに結びつけておいた。男は知らずに朝帰って行ったので、その糸をたどっていったら大池の中まで続いており、その男が大池に住む大蛇であることがわかった。それを知って大蛇は二度と男になって現われなくなったという話。
今日、端午の節句にコイのぼりや武者人形を飾るのは、春のひな祭りと同じく、武士階級の真似事であろう。
十八、氷室
昔は製氷技術がないので冬の雪を冷室に解けないように保存して、夏季に上流階級の人々が口にした。それが宮中の一つの儀式となり七月一日に氷を用いたのであった。また、加賀藩でもこの氷室の氷を将軍に捧げるため、遠路を江戸まで輸送した。しかし、一般の農家ではこの日は冷い氷のかわりに「いり米」を作って、娘の嫁入先や親類などへ配った。このいり米は貯蔵しておいたもみを蒸しあげて干し、もみぬかを取り去ったものをいって作るもので、使い残しの種もみでつくった。食生活に余裕が出てくると、砂糖やあめなどをまぜたり、豆やお菓子を入れておいしいものをつくった。今は自家製の労を避けてまんじゅうを金で買って配るようになった。
十九、虫送り
呼び名のとおり水田の害虫駆除の目的で始まったらしいが、その発祥起源は明らかでない。「飛んで火に入る夏の虫」のことわざのとおり、昔から本村では盛夏土用入り頃の七月二十日に決められている。たいまつの火明りは当然だが、必ず村の大だいこがともなうのはどういう意味なのか。ともかく昔から肝煎、区長の家につるされた村の大だいこは村に一大事があったり、村人の一斉的行動や通報の際打ち鳴らされたものであるから、この虫送りにも用いられたのであろう。陣太鼓、ほら貝、警鐘などと同様な意味で、実に集団の士気鼓舞に適していた。この虫送りについても面白い伝説がある。
長享二年(一四八八)の一向一揆の際、一向宗徒であった百姓衆の大軍が、富樫政親を高尾城に攻めたてたため高尾城は落ち、のがれた政親ほ鞍ヶ嶽山上からはるかに石川平野を望んだところ、なんとうんかのような百姓の大軍が続々攻め寄せるではないか。「おのれ百姓どもめ、このうらみはあの世へ行っても必ず報いてやるぞ」と叫んで、愛馬もろとも山頂の大池に飛び入り果てた。それから以後は政親の怨念がうんかに化身して毎年百姓の作る稲に群がり、大被害をおよぼすということで、この政親の霊魂をしずめるために虫送りが行われるようになった。
と、いうことである。いかにも一向宗徒である百姓衆の間に生まれそうな語り草である。
この虫送りの行事は、本村ばかりでなく郡内の近村にも行われているが、その様式規模は種々雑多で、各部落ごとに思い思いに行う村、一斉に行っても毎年継続しない村、部落ごとに若者の示威行動がけんかざたになり中止した村などがある。本村では随分昔から行われていたそうで、とくに村一円の統制ある秩序と協調的行動により、毎年継続的に行われてきた。戦時中は本村のみならずどの村も中断されてしまったが、戦後の復興とともに志ある識者のすすめで再び戦前のとおり復活した。
長い夏の日も午後八時頃になると既にたそがれが迫り、主催する青年団の企画に基き村の中心にある校庭(現在は県農業試験場前の広場)から、行動開始の合い図に花火が打ち上げられる。各部落では前から準備された子供達のたいまつ(昔はたばねたまきであったが、のち青竹の中に石油を詰め、現在は空きかんに石油を浸した布を詰める)に火が移され、青年達が大だいこをかついで威勢よく打ち鳴らしながら子供達のたいまつの後に続く。会場に通じる東西南北四線の道路はそれぞれ数部落のたいまつとたいこが連なり、粛々と十字型に行進するさまは実に勇壮で情緒ある光景である。会場には中心に大かがり火がたかれ、合い図とともに十四の大だいこが一斉に会場へなだれ込み、かがり火を囲んでたいこの競い打ちが始まる。はね踊りながら打ち鳴らすはち巻き姿の若者の威勢のよさは、全く観衆を魅了せずにはおかない壮観そのものの絵巻きである。
次に退場の合い図に従い、各たいこは一斉に打ち鳴らしながら帰途につく。続いて観衆は次の会場である相撲場に押し寄せ、子供達の草相撲が始まる。ちびっこ力士は家族の者や部落民に励まされ、両目をつり上げて闘志満々、観衆も手に汗を握っての観戦、夜のふけるのも知らない。
このような郷土色豊かでなごやかな、しかも古くから引き継がれて来た本村の伝統ともいえるこの年中行事は、世の中がどんなに変わってもいつまでも残したいものである。
二十、白山登山
朝夕仰ぐ白山は昔から白山比咩神社祭神の化身として崇敬されて来た。とくに水の恵みを受けての米作り専業である本村においては、男は一生に一度は登山して奥宮に参詣することが慣例となっていた。毎年、青年団の事業として白山登山が計画され、今日のように便利な道路や乗り物は思いもよらない時代だから、まず山びよりのよい七月中旬過ぎの季節を選び、かさにござのわらじはき、金剛づえをたよりに鶴来町から悪路難所を越えて登頂した。このような登山は明治初年から昭和の初め頃まで続いた。その後は電車やバスが麓まで通じ、登頂道路も改修され、軽装でしかも女や子供まで楽々と簡単に登山出来るようになったため、水のお礼参りよりも、スポーツや行楽気分で登る者が多くなった。
二十一、盆の七日ぶ
旧暦の七夕の日であり、お盆との関係はどういうのかわからないが、本村では昭和の初め、忠魂碑の建設とともに毎年この日を招魂祭と定め、碑前において盛大な慰霊祭が厳修されて来た。
戦前は当日を村一斉の休日とし、青年団主催の古典じょんから盆踊りが慰霊祭協賛としてにぎやかに行われてきた。戦後は進駐軍の監視で遠慮していたが、その後復活し、現在も継続されている。昭和三十年、野々市町合併後は富奥地区で忠魂碑保存会を設立して招魂祭を挙行し、地区の青年により同様に盆踊りが盛大に催されている。
このじょんから踊りは、郡内他の町村にも種々伝えられており、その歌詞も酷似したものもあるが、富奥じょんからの節(譜面後出)は郷土の世俗の中に生まれた純ぼく味豊かな独特の謡調である。時の流れと急激な世相の推移を考えても、ぜひ後世に伝えたい村の遺産の一つである。
二十二、お盆
都会では新暦の七月盆になったが、農村では依然として八月の旧盆が続いている。これは農事作業の繁閑関係で、かえって好都合であるからであろう。昔から家々の貸し借りや商いの請求支払いは年二回、盆と暮れにきまっていたが、経済流通の繁雑高度化にともない、大正の頃から都会では毎月末精算に変わり、本村でも戦後になってから都会風に移行した。これを盆払いと称し、貧困な家では「盆越しゃ出来ん」といった。また、子供達が野鳥や昆虫などを捕えて外へ放す時「盆に金持ってこーいヤ」と呼び、奉公人の雇傭関係も「盆ぎり」と称し、給金の精算や再雇傭契約も行われた。娘の婚家や常日頃世話になっている家への御中元は「盆礼」と称し、娘の婚家へはいなだ(ブリの乾魚をわらづとに包んだもの)が用いられた。
まず、十二日までには墓掃除、線香立てや花立て、キリコ(薄板屋根で四角四面紙ばり、南無阿弥陀仏が書かれている)かけの準備を整え、仏壇仏具の磨きをしてお盆を待つ。お墓参りは十三日夕方から行われ、キリコに灯が入り墓参の客人もキりコや線香、花束を持って自分が生まれ育った里の家へ孫などをつれて来る。十四日はどの良家も客を迎えてにぎやかな話し声に満ちる。これらの客人は方々に縁付いた者、遠い都会の学校や職場で修業中の若者、その二世、三世までにもおよび、その接待で家族はてんてこ舞い。しかし、年に一度、生家をたよっての墓参客であるから墓下の祖先も目を細めて喜んでいられるだろうし、まして一層かわいい外孫などが少々いたずらをしても気にもしない。墓参の客人は灯明のついた仏壇に礼拝してから墓場に行き、近くのお寺から坊さんも頼んで墓お経をあげる。
お盆は自分の生命の原点である祖先の霊前で語り合う時である。田舎の生家は広く涼しい。うちわ片手に横になり四方山の語りは尽きなかった。また、方々の部落ではいろいろな趣向の盆踊りが催されていたが、野々市合併後、町一円の盆踊りが中学校で開催されるようになって消え去ってしまった。この意義ある楽しいお盆も十六日で終わり、お盆客も名残りを惜しんで大水の引いたように帰ってしまい、部落内はもとの静けさにもどる。それからがいよいよ秋の取り入れの農繁期である。
二十三、魚とり
明治末期に七ヵ用水の全面的改修工事が実施され、その施設配備が完成されると毎年一回、その点検、補修のために全用水の取入れ水門を閉じて停水が行われた。かんがいの必要がない九月十日頃、一昼夜か二昼夜の間停水する。ちょうど秋の取り入れの最中で、ネコの手も借りたい時であったが、子供らは逃げ出すように川に走った。この頃は各用水の河川は柳株や深い淵が所々にあり、水も非常に清く、川魚も実に多かった。子供でもバケツに一杯の漁獲は珍しくなかった。しかも、日頃食卓に魚料理のまれな農家では絶好のごちそうであった。だから少し手先の器用な大人達は、昼の仕事を終えて夕暮れから出かけた。本村は富樫用水、郷用水の本支流が流れており、川の中では隣部落の人とあいさつをかわし、暗くなるとたいまつやたき火をしてワイワイ騒ぎながら競って魚を追った。獲物は上々だが、昼仕事に疲れた女達ほ顔をしかめて料理をしていた。ぬれよごれた衣類やせんたく物が積まれているのを、処理しなければならなかったからである。
大漁の家では一日で食べ切れず、幾日も食べ続けた。魚は食べてしまっても、楽しい思い出は残った。とかくこのような話題は天狗話に通じるものである。穴に手を入れカニに指をはさまれて泣いたこと、大きなコイがふところに飛び込んだこと、大きなナマズを捕え、ツルリと逃げられたことなど、今はなつかしいものとなった。
二十四、秋休み
秋の取り入れ収穫作業が終わった祝いと休養である。晩生品種が多かった昔は取り入れも随分遅かったが、大正時代から千葉錦など早生種が主体になると十月中旬にはほぼ終わった。
その後、極早生種が作られたり、農機具の発達で取り入れ作業がはかどって九月中にほぼ終わるようになった。とくに当地方は全国的に早場米の産地として、一時(戦後)早場米奨励金も米価に付加されていた。秋休みは新米のご飯やモチが食べられ、それを親類や秋の作業の手伝いに頼んだ家へも配った。もちろん人夫賃の精算もつけて持参した。最近は稲刈り移動斑が能登方面から出動したり、機械の発達と専業農家の減少で、日曜農業が多く、個々のペースで終わるので、一斉に秋休みを行うことができなくなったようである。
二十五、秋祭り
秋の収穫祝いでは一番の神事で、各部落では年中最大の祝事が氏神様を中心に種々様々なにぎわいで催された。中林・粟田新保の獅子舞い、上林の祇園喋子(ぎおんばやし)、その他各部落では屋台を組み、芸人を外から招いて浪曲、講談、手品、曲芸、漫才、俚謡、舞踊、芝居、琵琶唄などが若衆の世話で演じられた。映画もレコードもまだ普及していない時代では、これらの演芸物はたいへんな楽しみであり、近在部落や遠い縁故関係の者まで集まって来た。祭りが近づくと、若衆に何日も前からそのけいこや準備に熱中した。また、神社を中心に数十㍍の大のぼりや中小の流れ旗が立てられた。大きなのぼりなどを立てるのは大変なことであった。それは「旗の棒起こし」と称し、村総出で古老の指し図で工夫を凝らしたそうである。大小色とりどりの流れ旗が宮の森に映え、ハタハタと音をたててなびく様は一層祭の気分をかきたてた。夕方ともなれば大ちょうちんやぼんぼりが並び、各家々の前には様々の絵模様のあんどんがほんのりと照り、街のネオンなどと異なった情緒を添えていた。祭も終わる頃、直会(なおらい)の酒宴が催され、時には松任や鶴来の遊廓から芸者を呼び、若衆はのめやうたえの楽しい一夜を明かした。
昭和の戦時頃になると若者は出征して少なく、また、銃後の自粛から段々祭りはさびれてしまった。戦後はラジオやテレビによる個々の家庭の娯楽が多くなり、汗水流す旗の棒起こしなどは敬遠され、神主さんだけの神事になってしまった。
二十六、学校の運動会
この秋祭りに前後して学校の運動会が花やかに催された。その頃の運動会は単に学校教育の手段として行われたのでなく、生徒を中心にその社会環境をむ含めた村民の集いであり、村民が学校教育の場を理解する機会でもあった。
朝食頃学校の運動場から花火が打ちあげられてその決行が知らされると、子供達は勇んで登校する。この日は村中一日休みで、女達は弁当のおむすび(おにぎり)や手前料理をつくってお重箱に詰め、老いも若きも誘い合って見物に行く。部落に残る者は病人くらい。広い運動場の回り一面にむしろが敷かれ、一家、一族、一部落の団らんが始まる。声援せ笑い声が秋晴れの空に響き、音楽隊がかなでるにぎやかなメロディが士気を鼓舞し、陽気なふん囲気を作り出す。この音楽隊はレコードのない時代、街の若者など趣味か副業的につくったブラスバンドであり、当時はもの珍しい存在であったので方々から依頼されて出張した。
出場種目は学校の生徒ばかりでなく、職員(先生)、来賓(村の公職有志)、父兄、青年団、婦人会、幼児、他校選手など多様であった。秋晴れの一日は実に楽しく、さらにその日一日広めた見聞が、後日各家々や部落内の話題として花を咲かせた。
これが次第に発展して大正末期頃から村民体育の見地から社会体育大会が催されるようになった。
二十七、報恩講(ほんこ)さん
真宗王国である当地では宗祖親鸞上人の御恩報謝の表示として行われたが、単に宗教的行事にとどまらず、社会生活にまでとけ込んだ年中行事である。十月から十一月に入ると各寺で信徒を招いて報恩講の仏事が厳修され、ついでそのお手継ぎ寺のごんげんさん(住職)が番僧や門助(寺奉公人)を従え、門徒の家を訪れて正信偈、和讃、御文のおつとめをして回る。家々ではみがきもん(仏具の磨き)や仏壇の手入れをし花屋に特別注文した報恩講花を立て、報恩講モチをついて準備する。ごんげんさんは丁重に待遇し、食事には専用の朱塗りの高脚御膳(たかあしごぜん)を出して、主人白も接待した。御布施もその家柄として最も張り込み、おモチを土産にした。
部落の報恩講は御書様報恩講、若衆報恩講、尼報恩講とそれぞれ主催勧進元が異なる。御書様報恩講は村の仏事世話係(どうぎょうという)が主に主催する。若衆報恩講は部落の若衆(青年から少年まで)が主に世話する。その会計内容は各部落により多少異なるようだがその一例を見ると次のようである。
若衆報恩講かかり米
長男八歳(数え年)以上十六歳まで白米二升 糯白米二合
次男以下八歳以上十六歳まで 〃 一升 〃 一合
長男十七歳より三十歳まで 〃 三升 〃 三合
次男以下十七歳より三十歳まで 〃 二升 〃 二合
また、年下の若衆はざるをかついで家々を回り、野菜類をもらい集める。白米は換金して坊さんのお布施や酒、料理などの出費に当て、糯米は年上の若衆がモチつきして参詣者に配る。まず、坊さんの先導で元気な若衆中心に正信偈の大合唱から始められる。そのためにその頃の青年は冬の農閑期にお寺へ通って、正信偈のおつとめを習った者が少なくなかった。次にお坊さんのお説教が始まるが、年若い者はわからないから騒ぐ。「やかましい、騒ぐもんにゃ、うまいもんやらんゾ!」と一喝すると効果てきめん。そのあとおモチや若衆のつくった料理が幾さらも配られた。野菜類とこんにゃく、油あげの煮しめ、ダイコン、ニンジンの精進なます、黒豆の煮つけなど、とてもおいしかった。十七歳以上の若衆や部落の大人達は坊さんを囲んで一杯飲む。当時は部落の者が大勢集まって食ったり、飲んだり、話したりするのが唯一の楽しい娯楽であった。
尼報恩講は主婦達の世話でやはり若衆と同様に簡単な手料理をつくって参詣者に配る。その経費は部落により様々の方式であったが、若衆の米に替わって大豆を家々から集めるのが多かった。このような催しが年に数回、しかも昔から継続的に伝統行事として行われている。従って都会の町内住民の集いと異なり、部落民個々のつながりや、こまやかな人情味が生まれ、ひいては富奥村十四部落の協調和睦の精神となった。
二十八、お七夜(ひっちゃ)
親鸞上人は弘長二年(一二六二)十一月二十八日、九十歳の長寿で入寂された。その命日を中心にした七日間をお七夜と称して、一週間の精進日が続き、どの家も肉類を一切口にしなかった。わけのわからない子供や育ち盛りの子供には苦しかった記憶だけが残っている。もしこの精進が破られたり、なまぐさものをねだったりすると、「ばち(罰)ゃあたって口ゃむじる(ゆがむ)ゾー」と叱られた。この七日間、仏壇の勤めが毎日ねんごろなのはもちろん、近在のお寺では昼夜お参りごと(お講座)があり、部落の善男善女は誘い合ってお参りした。また、この季節に京参り(京都の本山参りと見物)をする者もいた。この京参りは鉄道開通前からあったらしい。よほど信仰の厚い者か私生活に恵まれた者でなければ出来なかったようである。
二十九、針供養
十二月八日を針せんぼと称し、女達の針仕事は一日休みであった。小学校に併設されていた裁縫学校、女学校、私設裁縫塾などでは一日針を使わず、折れた針、使い果たした古針を集めて感謝の供養をした。そのあとで小豆のだんご汁(のちお汁粉に変わる)を作り、余興などをまじえて女らしく一日を楽しんだ。なおこの日はふいご祭りといって鍛治屋のお祭り日であったが、農家には直接関係はなかった。
三十、山祭り
十二月九日。山の神様大山咋命をまつるお祭り日で、山林を所有する農家の多い粟田新保・下新庄などではこの日山仕事を休み、山に関係した精算などをしたあと直会(なおらい)の酒を飲みかわした。この日は山へ入ってはならない掟があり、山に入ると必ず神罰があると伝えられていた。
三十一、おか祭り
十二月十五日。この日は奉公人が一ヵ年の勤めを終える日で、主人の方では一年間の苦労をねぎらい、ごちそうをしたうえ給金や土産物などを与えて親元へ帰した。別名を薮(やぶ)入りとも称した。この日の料理の煮物の中には必ず油あげが入っていて、その切り口が内側になっていたら来年は来なくてもよいという暗示であり、外側であったら来年もまた頼むという主人の意思表示だったという話が伝えられている。近年の農家には下男や下女などがいないが、藩政時代から明治、大正の頃は、高持ち大作りの農家に数人の男女奉公人が雇われていた。それが縁でその部落内に縁づいた者も多くあったようである。
三十二、冬至
村の年中行事としての冬至は天文学的な意味でなく、四季の移りかわりの一節としてあった。この日にカボチャを食べると中風(脳卒中)にかからないという俗信が今に伝えられている。この伝えは単に農村だけでなく県内広くにおよび、本村の農家では夏に収穫したカボチャを貯蔵して置き、冬至が近づくと町方の親類などへ配る風習が今でも多少継がれているようだ。
三十三、正月モチつき
十二月も二十日を過ぎると、もう各家では正月のモチつきが始まった。中には二十八日精進モチ(宗祖親鸞の命日で精進日)、二十九日苦のモチと称する家もあった。ともかく昔は自家消費の間食用、贈答用などモチつきの量は非常に多かった。かきモチ(薄く切った干しモチ)はぜ(モチをさいの目に切り、干していった)きねまき(大きな軍配や巾着型のモチを大黒柱にかける。外孫の家へ毎年贈る)、まい玉(まゆ玉、しだれヤナギの枝にまゆのように色とりどりのモチの玉をつけ、外孫の家の飾りに贈る)鏡モチ、切りモチ、よもぎ草だご、ごんだモチ(粳米をまぜたモチ)乞食だんご、頼まれモチ(町方から頼まれたモチ)など随分大量のモチつきだった。朝もまだ暗い頃から夕暮れまで一日中つきどおしで、糯米一俵がふつうのところ二俵以上もつく家があった。だから男手の少ない家では人頼みまでしなければならなかった。
指の問からたれるようなつきたてのやわらかいモチを、うすからアズキなべや大根おろしのはちに転がし、熱いのをふうふう食べるのは、全く農家ならでは味わえない味といえよう。近年はモチつき機械が普及して、あのケヤキづくりのうすやきねが見られなくなったが、モチつき情緒を失ったモチの味はなんだか味気ない気がする。
三十四、部落万雑(まんぞう)
藩政時代、主税として村御印記載の物成、付加税に相当する打銀、鍬手米のほかに下部の雑費を総称して万雑といい、その徴集は藩でも認めていた。即ち、郡万雑、組万雑、村万雑があり、村万雑の項目は肝煎の給米、村小走手間、用水江代来、用水番人手間などが主要なもので、神社費などは別に氏子という世話役が運営していた。市町村制が施行された明治の頃は肝煎が区長に変わり、神社の運営管理は氏子総代にゆだねられたが、その維持費は区費内に含まれた。大正、昭和へと部落共同体が強化され、社会組織や経済面の拡大化にともない、多種多様の区費が必要となり、それらが部落農家の生活と密接な関係を保っていた。この区費の精算が昔のとおり万雑と称され、部落によっては年末一回または盆暮れの二回行われている。この万難の賦課法も昔はすべて持ち高によって配分したが、明治中頃から小作高も考慮するようになった。近年は農家も副業、兼業、出稼ぎなどが多くなり、部落により所得割、所得勘案率割、平均割など一様でない。また、万雑期日はその年により、部落により一定していないが、十二月二十日前後が多く、区長が提案兼司会兼議長の方法で精算協議が行われる場合が多い。閉会後に直会兼忘年会として一献傾ける。これはその時代により、部落によって規模様式正異なるが、随分累進的に発展するらしい。
三十五、〆縄づくり
お正月に神社の鳥居にかける〆なわや、部落の共同井戸に飾る〆なわは、年の暮れに部落の若衆の奉仕で新しくつくられる。新わらの太い〆なわに海草(主にホンダワラ)、うら白、ゆずり葉、ダイダイ、くしがきを飾ると、もうお正月気分があふれてくる。夕暮れに区長から酒肴が渡されると、年上の若衆はいい気げんで一足先にお正月気分に酔う。年下の若衆はお菓子やミカンをもらって帰る。この〆なわづくりは随分古い時代から各部落で毎年続けられており、神事だから戦時中も絶えなかった。これらの〆なわは正月十四日の左義長におろされて、青竹とともに燃やされる。
三十六、大歳
朝からどの家もすす払い、大掃除で忙しい。時には未払いの商人が最後の集金に回ってくる。「煤(すす)顔が首回らんと値切り払う」などの句もあるとおり、家計の最終総決算日でもある。神だなはとくに念入りに掃除して、天照皇太神宮の大麻を入れ替え、仏壇は磨き、掃除をして祖先の位牌も並べる。床の掛け軸や置き物もお正月にちなんだ飾りつけをする。そして神仏には御神酒、小判(小判型のせんべい、今は使わない)やミカンをのせた鏡モチ、松花、お灯明の飾りつけをし、学問の神様、土蔵の神様、台所のかまどの神様をはじめ、作業場(昔はにわという)農具(現在は農機一切や自動車など)の神様にはそれぞれ適当な場所に小判とミカンをのせた鏡モチを供えた。大黒柱には大きなきねまき(軍配型や巾着型の大きなモチ)をつるし、まい玉(まゆ玉)も美しく本居に飾った。これらのお供え飾り付けは主に男達の手で、女達は雑巾がけ掃除やお正月のお節料理をつくった。日頃の料理やご飯は年越しすると女の子が生まれるという俗信があり、夕食はなべざらいと称してほどほどに済ました。一年間のあかやよごれを入念に洗い清める大年のお風呂はとくに大水でわかし、男達から順にゆっくり入浴した。「花嫁や風呂できき入る除夜の鐘」はもう昔。「花嫁もテレビの前で除夜の鐘」と生活様式が全く移り変わった。下着から全部着替えた一家のだんらんは、年越しそばを食いながら、近在の寺々から響き渡る除夜の鐘を聞く。この除夜の刻に新しく福の神が屋内に御入来するという伝えから、玄関の大戸が必ず開かれた。昔の年齢は数え年だから、除夜の鐘を開いて年をとったわけで、人心改まる心境であった。とくにそんなことを意識出来る子供達は、急に大人に近づいたような気持でおとなしくなり、祖父母や両親の後に従い、神だなに礼拝したり、仏壇の前に改まって合掌した。除夜の鐘を聞かずに眠ると顔にしわがよるという迷信を信じて、眠いのをがまんしていた子供もあった。こうして一ヵ年間の支払いも済ませ、あかも洗い流して着替え、身も心も清々した一家は幸せな初夢を期待して床に入った。