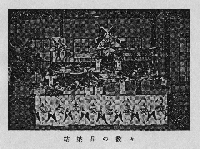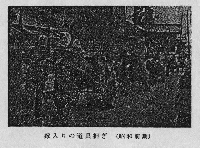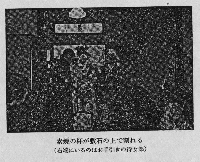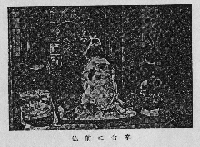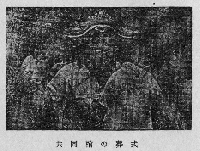<< part2へ [part3]
==第三節 冠婚葬祭==
第三節 冠婚葬祭
一、概要
明治の新しい時代を迎えたといっても、長い藩政下にかもし出された封建的な社会は容易に改まらなかった。とくに縁故関係を生む結婚成立の基本や様式は、その地域の社会性を無視することは出来なかった。また、葬祭においても宗教的仏事の規範はともかく、その規模、様式は地域独自の社会性に順応しなければならなかった。そして移りゆく時代の流れの中にも、常に地域の社会性が合流して、これらの慣行、様式が築かれて来た。本村は城下町金沢の近郊地域として、直接、間接に武家社会の格式、様式の影響を多分に受けてきたと考えられる。このような観点から本村地域に行われてきた冠婚葬祭について、古老の伝承を資料として記してみよう。
二、結婚
婚姻圏 昔は道路による地域交流が主であり、耕地整理前の頃はきわめて不便であった。従って隣村との交流は、遠近距離関係より道路関係が大きく影響することが多かった。当時の道路網は城下金沢に通ずる必要性から、東西より南北に通ずる経路が割合便利であった。一方、この時代の婚姻成立条件では本人同士の意思は全く無視され、家柄持ち高、世間の風評などが重要であった。だからそのような条件が明確に察知できる部落内の婚姻関係が多かった。しかし、小部落で似合いの候補が見当たらない場合、道路関係のある隣村との婚姻債向が多かった。大正から昭和の代になって交流社会が拡大すると婚姻圏も拡大し、戦後は県外に伸びるのも少なくない。このほか河川の流れに沿い、川上から迎えるのが川下から迎えるより幾分多いようである。
結婚適齢期 一様ではないが全般的に昔は随分早婚の傾向があった。明治中期頃までほ男子は二十歳前後(以下数え年齢)、女子は十七歳前後であった。封建制時代では嫁は農家の働き手としての意図が多分にあり、学校教育が実施されていないことも早婚と関係があった。大正から昭和になると義務教育の延長、男子の兵役のほか、本村では青年団や裁縫学校など青年団の活動が他村に比して普及していた関係もあり、男子ほ兵役を終えた二十五歳の厄年前後がふつうであった。戦後はさらに結婚年齢が延びる傾向になってきている。
縁談 男尊女卑の世では男性側は能動的、女性側は受動的で、嫁捜しは公然と積極的な行動が許されていたが、娘の婿さがしは養子とり以外口にすべきでなかった。それも男性自身が嫁捜しするのでなく、すべて親の領分であった。胸中いかに思っている娘があったとしても、本人自ら口にも行動にも表してはならなかった。少しでも表すような男は世間から冷笑されるから、やせ我慢するよりしようがなかった。
長男が適齢期になっても嫁捜しをしない間抜けな親に対しては、長男が遠まわしに「まま、おつけ」と大声で飯茶わんと汁わんを同時に突き出す。それでも感づかなければ、「こんににゃ(この家では)女手ゃたらんわい」といったという落語のような話まで伝わっている。
ともかく、婚姻関係の基本は外観的客観情勢が第一義であり、それに適合しない二人の直接行動はやましい行為として親の許しどころか、親類近隣社会からも非難の風評が強かった。このため親は私情をこらえて世間の義理を立てなければならず、遂に勘当されるか、あるいは「せめてあの世で添いましょう」といった悲恋物語となるケースも少なくなかった。
両親が嫁捜しをするにはまず親しい人や経験ある世話好きな仲人に依頼する。仲人はいろいろな角度から勘案して適合する家柄の娘を見付け、両親に持ちかける。両親は思いに叶った良縁でもさらに念入りに陰見、陰聞きをして検討する。この陰見、陰聞きは先方に感づかれぬように種々のテクニックを要し、一方、適齢期の娘はいつどこで見聞きされているかもしれず、常に行動に注意し、容姿を整えておらわはならなかった。
これらのいくつもの検討や吟味を経てパスした縁談は、初めて本人や親類に打ち明け、相談されて、いよいよ正式に仲人を通じて娘方へ持ち込まれる。娘方では一度や二度の縁談では内心どうあろうと、謙遜(けんそん)の口上で辞退するのが常識であり、礼儀でもあった。息子方の両親や親類の方もこれに対して幾度となく礼を厚くして懇願する。昔から「玄関の敷台が低うなるほど」とのたとえ言葉があるほどで、ようやくその誠意で娘方の心が傾くと、今度は娘方によって息子方の陰見、陰聞きが行われる。その結果、娘方の両親や親類の納得を経て初めてお見合いが行われるのである。
見合い まず場所は娘方の本居(おい=居間兼応接間)で行われるのがふつうである。定刻(昼間)にはいつも着なれない晴れ着に足袋姿の息子が、父親あるいは母親と同伴、仲人の先導で娘方の家に向かう。娘方では玄関先から美しく掃除して待っている。息子はあいさつ、口上一切を両親にまかせ、無言で会釈するだけで視線もヒザの先より上がらない。しばらくすると花嫁候補の娘がお茶とお菓子を持ってあらわれる。こちらの方も視線は腰元より動かさず、相手の顔を見ることはない。せっかく出されたお茶はだれも飲んではいけない。話が茶話になって流れるという縁起があるからである。また、お茶菓子も三個は禁物。三角関係は角が立つ、双方一対が芽出たいというわけである。
お見合いが終わるともう縁談は九分九厘成就、あとはよほどの予想違いが突発したり不祥事がない限りまず安泰。万一、見合い後に破談することがあると、原因はともかく、娘は一生の傷者に陥るのが当時の風習であり、お見合いは軽卒に出来なかった。「お見合いなら五回もしましたよ」と得々と語る現代娘の世相では、昔の封建的律義の結婚様相など想像もつかないであろう。
たもと酒(手打ち酒、一升酒ともいう) これは婚約の予約を確認する祝い事であって、仲人が婿方の一生を誓う心をこめた一升の酒を持って嫁方の神棚にささげ、ともども柏手を打って誓約と祈願をし、そのお下がりをいただく祝いである。この時に次の本酒の日程や条件を話し合うのであるが、とくに〆金(結納金)などは直接ロにすることをはばかり、双方の仲人が互いにたもとの中で指折りかわしてその数量を交換したから、たもと酒と称するようになったといわれる。
本酒(結納) 事が順調に進むと次は結納の本酒祝いである。吉日が選ばれ、礼服姿(紋服)の婿方の父親か母親と、近い親類の者につきそわれ、二人の仲人は結納の品々をわくだいと称する箱型の荷台(一・五㍍に二・五㍍ほどの木製で黒塗りの箱型台)に飾り、長い棒でかついで嫁方へ向かう。嫁方ではこの結納の品々をありがたく受け、大黒柱の前に並べて飾る。お客一同を出居に案内し婚約祝いの酒宴が開かれる。料理は本職の料理人が仕出し、お酌人は嫁方の親類の者が寄り集まって接待する。酒宴は約三時間以上も続き、お酌人は酒の酌ばかりでなく、縁起のよい小謡曲(こうたい)やめでたい様々の歌詞の歌を歌って客人を接待する。この場合の歌の文句では、出る、わかれる、泣く、嘆くなどの語句は禁物で、よく注意しなければならなかった。
そのうちに花嫁候補の娘も着飾って母にともなわれ、母の口上であいさつに出る。客人は心置きなく十分に接待され、ごちそうの大風呂敷を手に帰途につく。
この結納本酒も地方により、時代により次第に様式が変わっている。本酒を省略して結納をかわすのは町方に多くこれはすりかえ酒ともいう。また、手打ち酒や本酒は元来婿が全然参加しなかったが、戦後町方などで婿が出席するようになり、農村でもそれに同調するようになった。結納本酒で婚約は確実となり、現在では公然と二人の楽しいデートが挙式の日まで続き、挙式や新婚旅行の計画なども語り合う。もう仲人の必要もないような状腰であるが、昔は両人ともますます自重、あらぬうわさなど立っては大変と婿は家業に一層精を出し、娘は家に引っ込んで嫁入り準備の縫物をしながら、両親から嫁入り後の心得などの教示を受け、外出はあまりしないようであった。そして両親はその家の財力に似合った嫁しこみ(おこしらえ)に専念した。昔から「娘三人持ったら家が傾く」とまでいった。もちろん娘がかわいいせいだが、世間に対する義理と見栄も加わっていた。
箪笥(たんす)かき(道具調度品運び) いよいよ嫁入りの当日。まず午前中は道具運びで、婿方から数人のたんすかきと称する人が嫁方の家へ行く。お膳が出て祝い酒の接待を受け、酔いが十分まわった頃、たんすかきの行列が出発する。しこみの規模にもよるが大きい方では数十人のたんすかきが双方から集まり、そろいのはっぴ、はちまきまで新調したのもあった。青竹をツエにたんすかきうた(道具かき唄、長持唄)をうたい、道一杯にねり歩いて嫁方の村を出る。たんす、長持、様々の道具、わく台にはそろいの染色に嫁方の紋所を染め抜いた美しいゆたん(覆い布)を掛け、わらで作った鶴亀(俵を主としたわら細工で鶴と亀の中には赤飯のおひつと生菓子のおひつが入れてある)おみやげ(結納の場合と同様)を飾ったあくだいなど、長く続いた列は全く絵巻物のように情緒あふれる美しい光景であった。道中通過の村へ入るごとに小休憩、酒樽口に刺した細い青竹の飲み口で、通りがかりの人々に祝い酒をすすめた。
婿方の家に着くと、今度は嫁方のたんすかきが招待される。青竹のツエは二度と使わない縁起でみんな折り棄てられた。たそがれが迫る頃、ごちそうの風呂敷包みなどをぶら下げ、千鳥足のたんすかきは愉快な鼻歌で帰って行く。娘などがからかわれてキャアキャア家へ駆け込んだりする光景は農村の結婚シーズンである晩秋や早春の吉日などに見られ、微笑を誘う情景でもあった。
たんすとともに運ばれた鶴亀の俵から出された赤飯や生菓子は、調度品として運ばれたお重箱(嫁方の家紋入り、金巻絵)に詰められ、房かけ(ふさともいう、しおぜなどの厚い絹織地に嫁方の紋を染めた四十五㌢ほどの四角い房付)で覆い、家紋染めの風呂敷に包んで近所や親類へ配り歩いた。戦後を経た現在では生活水準、様式がともに高級化し、和洋双方を整え、機械化電化の調度品が加わり、中には自家用車や応接室セットまで積み上げる。娘を持つ親の負担は一財産に価する出費であろう。
結婚結納目録の一例
寿
御神前
御神酒 壱樽
御鏡 壱重
御勝男 壱連
御仏前
御供花 壱立
御香 壱箱
茂久録
熨斗
家内喜多留 壱荷
寿留女 壱連
子生夫 壱連
友白髪 壱樽
御礼服 壱着
末広 壱箱
御父上様 五福 壱反
御母上様 五福 壱反
御祖母上様 毛布 壱敷
御弟様 五福 壱反
御妹様 五福 壱反
御仲人様 毛布 壱敷
右之通幾久敷御寿納被下度願上候也
昭和八年三月吉目
○○家
○○家殿
嫁入り 日がとっぷり暮れて夜空に星のきらめきが冴える頃ともなると、婿方では今や遅しと待ち尽くす。村の端で見張っていた者がチラチラちょうちんの灯が括れるのを見つけるとすぐ報告、婿方の家族親戚一同が晴着姿で一様に立ち上がり、それぞれ係りの部署に着く。
そして婿の着付けも出来た頃、婿方親類の者達のかざす灯で数台の人力車が見えてくる。車のきしる音にあわせて車上の文金高島田にかかる「てぼそ」(つのかくしともいう)が揺れる風情は実に印象的であった。主演者である花嫁の一挙一動は取り巻く数多くの注視の的で、全く慎重そのもの。客人の一行は主客の花嫁、介添えの母親、父親、近い親戚が数人、両仲人と十数名にもおよぶのがふつうであった。玄関には婿方、嫁方双方の親類から寄せられた「せいろう」(中に生菓子が入る)が積み上げられ、結納品同様大黒柱の前には嫁方からのみやげ品、祝いの品々が所狭しと飾られている。花嫁は「おかいとり」(うちかけ)のすそを手ばさみながら玄関から敷き台の前に向かうと、三宝に据えられた素焼きの杯が待っている。花嫁がうやうやしく杯を手にすると、婿方の飲料水と仲人が持って来た嫁方の飲料水が同時に注がれて混合される。それを花嫁は静かに口つけして返す。返された杯は婿方の主人代理が玄関の敷き石の上に落とす。素焼きの杯が見事に割れると、居並ぶ者一同が「アーめでたい」と満足するわけである。もしも割れなくても二度とやり直す事は禁物だった。割れなかったときの被害はみな花嫁に寄せられ「この嫁は処女でない」とか、後日「強情な嫁じゃわい、杯や割れんだわけじゃ」と姑の嫁いじめの材料になるからである。敷台に待っている待女郎(婿の近親の少女が化粧して晴れ着で待つ)お手引(羽織袴の少年)の二人(雌蝶雄蝶と呼ぶ)がかわいい手を差し出して花嫁の手を引いて家の中へ誘導する。
結婚式(仏式) 花嫁は本居から友禅染めののれんをくぐって出居の仏壇の前に進み、随行の客人達も後に従う。婿方の主は仏壇の前に出て、嫁方から寄せられた松花を仏前に供え、朱色のローソクに灯明をつけ、鈴を鳴らして合掌すると、花嫁や客人一同も敬虔な祈りをこめて合掌する。次に花嫁はまた手を引かれてかぎの間(出居の横の奥の間)に導かれる。かぎの間には赤青の座蒲団が並べられていて花嫁は赤い方に座るのである。初めて紋服袴をつけた婿が緊張して入ってくる。(いそいそとうれしそうな態度ではいけない)二人並んで座ると介添えの者一同が退出する。今度は一組の夫婦(近親の夫婦)が紋服姿で入ってくる。この夫婦は契りの杯である三三九度の介酌人であり、三宝にすえられた素焼きの三つ組みの杯をまず花嫁にすすめる。花嫁が三つ組みの上の小さい杯を手にすると、介酌人は雄蝶、雌蝶の熨斗(のし)で飾られたかんずる(ひさげともいう。鉄びんのようなもので柄杓に代わるもの)で冷やの神酒を二、三滴注ぐ。花嫁は口づけていどに飲み終わると、懐紙で杯の端を拭って杯を置く。その間に三宝にのせられた肴(松葉形や巻いたするめや昆布)を青竹の箸で花嫁の差し出す懐紙に置く。一礼して今度は花婿の前に進み同様に酌し、最後に花嫁に酌して終わる。
三つ組みの杯は大中小とも酌するのを略して上の小杯だけを用い、三つ組みを三度回すから三三が九、即ち三三九度の杯と称するわけである。この間、部屋の一隅の屏風の陰で高砂の一曲を謡う。これをかげ謡いという。これで夫婦の契りが終わったので花嫁は退出し、以後は記念写真に出るだけである。出居には座ぶとんが並び、最上座は花嫁、両脇に花嫁の両親、片側は花嫁方の親類、片側は婿方の親類が並び、両仲人は最下座に座を占める。次の下座には婿方の両親、家族が座し、三三九度の杯のお流れをいただき、初めて親娘親類の契りが結ばれる。
披露宴 式が終わって中入りと称する休憩中にお茶(昆布茶)とお菓子(紅白寿煎餅に松葉)が出され、花嫁方と花婿方の招介とあいさつがかわされる。あいさつのあと花嫁の両親や親類の代表が案内されて近所の家々へあいさつに回るり。その間、写真屋が新郎新婦の記念撮影をする。次に落ち着き餅と称する小さい紅白餅の小膳が出される。花嫁は全部食べずに白い方をおわんに残す。これは膳が引かれたあとで婿に食べさせる慣例があって、はにかむ嫁をとらえる台所手伝い女衆の一興でもあったらしい。
披露の酒宴の始まりはまず三つ組み杯と称する金銀巻き絵の美しい杯が大中小重ねてすすめられる。花嫁から順に回り、その間とり肴(さかな)とともにお酌人の祝いうたとして高砂、鶴亀、猩々、羅生門、羽衣などの小謡が謡われる。この三つ組み杯までほ酒宴の形式にのっとり一座は威儀を正している。続いて会席膳が運ばれ、お酌人の案内で男ははかまを脱ぎ、あぐらでくつろぐ。流行歌や様々の芸事が披露され、笑い声や雑談も加わり一段とにぎやかになる。だが、古来からの縁起で泣く、別れる、嘆く、出る、帰るなど不吉な語は一切禁句であって、注意しなければならなかった。また、その間に花嫁は色直しと称し、控えの間に入って着替えをする。そのたびに介添えや女客は座を立って足を伸ばすことが出来た。この色直しは、花嫁の衣裳が多いほど数多く、結局色物紋付を多くしこんだことになるので、何回色直しをしたかが女衆の話題になった。
花嫁が色直しなどで控えの間に入ると、双方の親類方から部屋見舞いと称し生菓子や果物などが差し出され、介添えはそのつど花嫁に代わって、謝礼のしるしに金一封をおひきと称してお返しした。この部屋見舞い品は花嫁の方からおすそわけといって双方の親類方に配られた。宴席は飲むほどに、酔うほどにますますにぎやかになる。嫁方からお酌人や料理人、台所手伝い衆に御祝儀の金一封が贈られ、子供たちの歌や踊りなどがあるたびに花嫁方から御祝儀が贈られる。また、待ち女郎には嫁方から、介添えには婿方から御祝儀が贈られ、祝儀の包みは何個も準備しておかねばならなかった。夜もふけて客方から「十二分におよばれしみした。どうぞこのへんでおひらき(閉会)願いみす」と何度か申し頼みがあると、今度は高脚ご膳が出され、客人は再びはかまをつけ、威儀を正して祝いの赤飯を頂く。その間に生の大ダイ、折り詰め、ひろぶた(盛物かご)鶴亀菓子折、引出物などが所狭しと運ばれる。ご膳が引かれると最後の大さかずきになる。まず、料理人が自慢の腕を振るった蓬莱山(約六〇㌢平方の脚付大盆の中に松を活けた山、豆を敷いた浜磯、昆布を漂わせた波型、大根細工の鶴、ゴボウ細工の亀、ニンジン細工の日の出などの盆景)が運ばれ、嫁方から贈られた双尾のにらみ大ダイのからむしが大皿(約五〇㌢径)にすえられる。蒔絵の三つ組の大杯(酒が約一㍑から二㍑入る)が主客から順にすすめられ、小謡が謡われる間に飲み干す。女客は酌加減されるが、男客にはなみなみとお酒が注がれ、更におっかいと称して追加され、容易に飲み干すことが出来ないが、返杯は飲み干さねばならず、無理してどうにか飲む。一巡して最後に婿方の主に納められる。この時千秋楽の小謡が一同から謡われ、主はなみなみ注がれた大杯をロにしながら、おっかいのお酌人に追われるように後去りに退出する。これで酒宴が終わる。
以上のように豪華な結婚様式は、米価が十円以上になり、農家の生活水準も高くなった明治末期から大正にかけての、相当高持ちの農家の実態である。従ってそれ以下は家柄財力に応じ、種々の段階があった。また、このような婚礼様式には一定の格式があり、その格式は藩政時代の武士階級の格式伝統に実によく似ていた。
昭和の戦時になると国民生活の自粛を求める声が出て、昭和十一年から生活改善運動が婦人団体を中心に、各部落常会で呼びかけられるようになった。その強調事項として結婚改善について次のように要望され、本村においても村の家を式場として、幾組かの挙式がきわめて簡素に行われた。
戦時中の結婚式
「結婚の改善」 結婚は人生の一大事なることを自覚し、慎重に考慮して厳粛にこれを行うこと。
一、式前
イ、媒妁人を厳選すること。適当な者無き時は社会教育委員、青年学校長など公職者にこれを依頼すること。
ロ、結納はふつうの帯地、はかま地代のていどとすること。
二、挙式
イ、会場は自宅または公共建物とし、神前、仏前においてとり行うこと。
ロ、新婦の服装は黒の紋服のみを用い、着替えをなさざること。
ハ、新婦の所持品は日常の必要品以上に出でざること。
ニ、祝意を表する贈物はなるべく数人連名にて永久性あるものを選ぶこと。
ホ、必ず清浄厳粛なる儀式をもってすること。
式次第の一例(仏前の場合)
一、一同着席
1、親戚来賓着席
2、新婦入場、仏壇の右側に着座
3、新郎入場、仏壇の左側に着座
二、司会者開式の辞
三、新郎の父、仏壇の扉を開き、灯明を点ず、一同礼拝
四、媒妁人誓詞朗読
五、誓詞に署名(新郎、新婦、両父母、媒妁人)
六、新郎新婦仏前にて礼拝、一同礼拝
七、新郎新婦正座に着く
八、新郎の父灯明を消し閉扉
九、媒妁の辞
十、あいさつ(新郎の父、新婦の父)
十一、祝辞、親戚総代(新郎側、新婦側)来賓その他
十二、司会者閉式の辞(挙式は時間を必ず守ること)
三、披露会
1、努めて時間の短縮を図ること
2、質素を旨とし交盃、大盃は絶対行わざること
四、式後
1、新郎新婦は氏神及び祖先の基に参拝すること
2、ただちに結婚届を出すこと
3、膝直し、三ッ日、五ッ目を廃すこと
4、新郎への土産は簡単な実用品にとどめ、新郎の側から祝い返しをしないこと
5、新婦の実家からその後の一切のつけとどけをしないこと
このような自粛改善は終戦後まで続いたが、戦後生活水準の高揚とともに再び華美な結婚式が復活し、花嫁衣裳も豪華になり、貸し衣裳が常態となった。式場も広い料亭などに移り、これら料亭などは神前式場を造り、一切請け負いとなった。また、挙式後はすぐ新婚旅行に出発するなど、すべて花婿花嫁中心に変わった。
お里帰り 花嫁は結婚後数日過ぎると、一度生家へ里帰りする。これは、なれない新婚生活に心身ともに疲れているので休養の必要があった。また、日夜娘を案じる両親に報告して安心させるためでもあった。両親は、どんな顔をして帰るだろうと心配して、いろいろおいしい好物を準備して待っている。初めての里帰りで婚家の姑も送って来るので、その接待に料理やお土産物も整えなければならなかった。また、姑が生菓子やお餅を持って来ると近所へ配り「出居」の上座にご膳を並べて接待し、帰りには折り詰め、大ダイなどの土産品を持たせて帰した。花嫁は姑が帰って初めて両親の下で心安く休養出来た。三日か四日滞在し、婚家に帰る時はまた、モチなどをついて母親が送って行き、休養のお礼をいって帰った。婚家ではそのモチなどを近所へ配り、嫁の帰宅を告げるのであった。
つけとどけ 「つけ」は「付ける」 「着ける」で、心を行動に表わす意味であり、「とどけ」は「物を届ける」即ち、思いを品物に託して贈答することである。嫁いで他人の中にいるかわいい娘を思う親の真情を、物品に託した自然な行動で表現したもので、「親」「娘」「姑」の社会的同調意識が一定のルール的風習を生み、さらに「やり身、とり身」といったように、固定的に形式化してしまったのが「つけとどけ」であろう。明治から大正へと農民解放にともなう生活水準の上昇につれ、一層その形態が増大し、ついには本末転倒して「形式的取り引き」のようになった。そこで生活改善運動として、その節減や廃止を心ある人達が提唱してきたが、一向に効果がなく、昭和の戦時体制下に至って自然に下火になった。が、戦後再び変わった形式的復興が見られるようになった。次にその発祥発展を明治から大正ころの一般的な例で四季を通じて掲げる。
この「つけとどけ」は娘を持った者には大変な負担であり、社会的に実に不公平な風習である。大正から昭和へと農家の経済が良くなり、とくに米所の本村など米価の急激な上昇にともない、自然とこの「つけとどけ」にも影響し何でも「里から、里から」と持ち込まれる習慣が出来た。おもちゃから衣服、子供乗物、入学時には「かばん」「くつ」「子供雑誌」など際限がない。人間のやむにやまれぬ親子の愛情から発祥した「つけとどけ」は、次第に義理と人情に、さらに人情より義理と虚栄にまで広がっていった。
年間のつけとどけ
年頭 正月二日頃 洒一たる、菓子箱など 酒だるはふつう二升入りだが、一升入りもあった。
寒モチ 正月二十日大寒人前 モチ四うすほど 一うすはうるち米約二升。
婿様ちょうわい 二月上旬ちょうわい時 特別料理ご膳、タイ折り詰めなど 婿様の年初めのちょうわいで、一晩泊めて接侍する。最も気の張る事柄であった。
節句モチ 四月三日前 菱モチ四うすほど 菱モチはモチ草を入れてつく。緑色粉も使った。押しモチを菱形に切ったもの。
いりんがし 同上 いり米四升ほど 種もみの余りをむして干し、もみぬかを除いた米をいりナベでいる。いり豆、いりはぜなどとともに砂糖つけをしたり、こん平糖などをまぜる。
さつき休み 五月末田植え後 かいモチの重箱 おはぎのこと。小豆あん、きな粉をつける。
端午の節句モチ 六月初め モチ三~四うす ちまきを作るかわりにモチをつく。形はちまきを真似て三角だ円形。
氷室 七月一日 昔はいりんがしであったが、戦後まんじゅうになった。
土用モチ 七月二十日頃 モチ四うすほど 白丸モチ、外にささげのとびつけモチ一重。
お盆帰り 八月二十日頃 モチ三~四うす、またはまんじゅう五十ほど
秋祭 十月中旬頃 赤飯一重すし一折 外にぜんまいの魚煮しめ、はべん、はやびすなどの重箱。
秋休み 十月下旬 かいモチ一重
報恩講モチ 十一月下旬 小白丸モチ一重(おかざりモチ)小豆どり一重 報恩講モチは仏壇に供えるため小さい鏡モチ小豆どりは小豆あんをつけたモチ。
ブリ初穂 十二月上旬 大ブリ一本 アラレが降る頃ブリは最高の味。「一斗ブリ」と称し、米一斗の値で中上のブリが買われた。婿方で半分を返し贈る例もあった。
御歳暮 十二月下旬 洒一たる 孫がある時「きねまき」または「きんちゃく」「まゆ玉」その他お年玉を持っていく。
三、出産から成人まで
コロコロダンゴ 花嫁は妊娠五ヵ月になると腹帯を締める。安産の神仏を祭る神社や寺院から受ける場合もあった。いよいよ臨月近くなると、初産の嫁は里に帰って過激な労働などをせずに休養する。里方では「コロコロと安産できるように」と祈願の意を込めて、「コロコロだんご」(昔はだんごで作ったが次第にモチになった)という楕円形のモチを作って、婚家や親類、近隣へ配る。婚家ではそれをさらに親類や近所に配り、安産を祈ってもらう。このモチをもらった家は必ず出産祝いを贈らねばならない。だから、むやみにだれにでも配ることが出来ないわけである。
出産 明治初年頃までは専門の産婆がいないので、村で経験ある「とり上げばば」が助産した。明治中期頃からは専門的講習などを受けた産婆が登場し、助産と育児の指導に当たった。やはり初めての子は男の子があととりとして望まれた。女の子ができるとだれのせいでもないのに、嫁は自分の失態のように婿や姑に対して気がねした。産婆は毎日通ってお湯をつかわした。
人工母乳が市販されたのは昭和に入ってからで、当時母乳の不足は「おねば」という炊飯の時に吹き出るご飯汁を取って飲ませた。その間「コロコロだんご」をもらった人々が、次々と出産祝いの布切れなどを持って見舞いに来る。姑は孫の顔を見たくてすぐ行くが、父親になった婿は自分の子を見に行かなかった。現在のわれわれには考えもつかぬ「バカ我慢」と思うが、昔は何かと「かかあに甘いバ力男」といわれることが非常な恥辱であったらしい。昭和の初め頃からほその傾向も少なくなったようである。
出産祝 出産後一週間も過ぎて母子ともに元気になった頃、出産の祝い事が行われる。婚家の姑や主だった親類を招いて祝宴が開かれた。その際、婚家からは嫁の栄養にと鮮魚かご、孫の晴れ衣などのおみやげ品を持参する。一行は健在な母子を確認し、ごちそうの風呂敷包みをぶら下げ、満足して帰る。
初産帰り 母子は里でともに健在に約一ヵ月を過ごすと婚家へ帰る。これを 「初産帰り」と称し、所によっては「孫渡し」ともいった。一ヵ月の間に母親になった娘は、里の母とともに御祝い品としてもらった反物や布切れを縫うのに忙しかった。帰る日になると、紋付姿の嫁に孫を抱いた母がついて行く。新調した美しい子供紋付が抱かれた孫に掛けられ、父親は子供タンスや乳母車、つぶら(今は使わない)祝いモチなどを持っていった。里方では「家が傾く程の嫁入りじこみ」に引き続いて「初産じこみ」と、その負担は大変なものであった。それらの運送も人力車や荷車がない時代は、やはり親類の者の肩を借らなければならず、一行を迎えた婚家では、出居にご膳を並べて祝い酒の料理をした。渡された孫は嫁や婿の子でありながら、その養育支配権は全く姑にあり、母親となった嫁は母乳を提供するだけであった。とくに不思議なのは父親になった婿である。自分の子供を抱えたり、ヒザに抱いたりしなかった。大正年代生まれの者は祖父、祖母に抱かれても、父親に抱かれた記憶はほとんどない。その理由は一つには夫が妻の手をかばうことを、姑に対し「カカにあまい」と思われてはいけないという配慮と「カカのしりに敷かれている」と世間のうわさがうるさかったためであろう。そして「ジイジ」が「ボン」(長男の愛称)を抱いて村など遊び回る光景を、世間の人々は「円満な家庭」と評価したのであった。
名付け 子の幸福な一生を祈った親の真情が、子の名にこめられているのは昔も今も変わりはないが、この時代、長男の命名が父親を飛び越して祖父の名と通じていた。例えば、
文右衛門-太三郎-文一-永三-健一
八郎衛門-三太郎-善八-三夫
のように祖父が自分で自分の一字を付けて命名したものか、父が配慮して祖父の一字をもらって命名したものか明らかでないが、孫の命名まで祖父の支配権が働いていたことは確かであった。半面、明治初年頃は文盲の父や祖父が多かったので、役場に届け出た際、役場吏員に相談して命名したのもあろう。その際、父親を差し置き、届けに行った祖父の心を汲んで吏員が命名したものもあっただろう。ともかくそれがその時代のうるわしい風習であった。
食いぞめ 生後百ヵ日、赤児も首がすわり、かわいい顔になる。まだ乳のみ盛りだが、昔からの慣例に習い、里から子供用の美しいお膳箱(昔は食卓がなく、各人が膳箱の中に食器頬を始末した。この箱は膳にもなった)におわん、さら、はし箱などが入れられ、赤飯と焼きダイが贈られる。形式的な祝いごとであった。これは次の子からは婿方で準備される。また、大正初期頃から記念写真が流行するようになる。こうして祝いながら育てられる子供も、農繁期にはだれも見守ってくれない。灰袋をお尻にはさまれ、「つぶら」に押し込まれ、誕生を過ぎてもつぶらの中で留守居をしなければならなかった。
誕生祝 満一年の誕生日のお祝いである。お里から「かいモチ」が贈られる。その「かいモチ」をお尻に投げつける。これは早く歩けるようになれというおまじないである。今の子は誕生頃によちよち歩くのがふつうで、「つぶら」で育った子は足が弱い。矛盾したようだが、昔は子守りに困った。それでいつまでも「つぶら」に押し込んでおくため、腰におもりまでつけて出られないようにしていたという。農繁期の留守居のためのこの「つぶら」も、各家により一定しないが、大正中期頃まで使われていた。
少年少女期 明治五年に初めて「邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめんことを期す」と太政官の学制布告があり、学校教育の道もようやく開けた。が、一般の関心は薄く、その施設も容易に出来ず、明治十二年の教育令制定に続いて同十九年に学校令が制定される頃になってかなり就学する者が出てきた。しかし、学校設備もさることながら、父兄の教育観念も低調で、男の子は忙しい農家業の手伝いに、女の子は弟や妹の子守りに使われ、就学する者は奉公人などを使う裕福な家の子弟が多かった。就学奨励のため、役場吏員や公職者、学校の先生まで各家々を訪問して、就学勧誘に努めなければならない時代であった。しかし、明治も中期頃になると、就学も高率化した。「おい、ボン(長男の愛称)ひんま(午後)からじぎゃあ(授業)なんじゃ。唱歌と体操か。ほんなら早じまい(早退)してこい。田んぼで唱歌うとうて、くわで体操すりゃいいが」といったように「学校は読み書き算術、算盤を習う所」と心得る親も少なくなかった。
四年間(後に六年制から高等科二年が加わる)で小学校が終わると、長男は家業を継ぎ、「おじま」(次男以下の通称)は「でっち」という「徒弟奉公」のため町方へ出て(住込み)、種々の職人見習い修行に励んだ。女子は家業の手伝いかたがた「裁縫」を習ったが、貧しい家では町方などへ「女中奉公」に出て親へ仕送りし、嫁入り時の「しこみ」のために働いた。村に残った長男や将来世帯を持たして分家する「おじま」は、「若い衆」といい、部落のヤングとして暇々に親の目を盗んでいたずら遊びもした。
しかし、明治末期に至り、富奥村の若者は他村に先んじて(明治四十二年)「富奥村青年会」(後青年団と称す)を、女子は「富奥村処女会」(女子青年団の前身)を結成し、青年の教養訓練と郷土の社会文化活動に貢献し、その成績はとくに優秀で、数々の受賞を重ねた。この青年の協調心が一致団結の旺勢な向上的村民性を築き上げ、農村に押し寄せる不況の嵐の中にも「一村一心」をうたい、「経済更生」で乗り切ることが出来た。戦後移り変わる世相にも、郷土富奥の美風が今も温存されている。以上のように教養と訓練によってたくましく成人した村人が、戦後の今日までもなお郷土発展の原動力となっているのである。
徴兵検査 明治六年一月に徴兵令が発布され、男子で満二十歳に達した者は徴兵検査を受ける義務が制定された。この頃は免役規則があって、戸主、嗣子、短冊(戸主の孫で将来家督を相続する者、または他家の養嗣子の者)は免除された。しかし、この免役規則は明治初期だけのことで、日清、日露戦役を経た後は軍国思想が強化され、古来の武士道復活の様相がますます旺盛になり、昭和の戦時に突入するに至った。この徴兵検査を受けた男子は初めて社会的に一人前に扱われ、現在の成人式同様であった。体格の良い者は甲種合格として入営した。
富奥村出身で入営した新兵の成長は優秀な者が多く、昇級率も良好であった。満期退営後は村に帰り、農家経営はもちろん、村の推進的存在として青年期は各方面に活躍した。富奥村が全国の模範村としてその名声を挙げたのも、この青年期の人々がその基礎を築いたのであった。大戦時中これらのたくましい青壮年が多数、戦場で不帰の英霊と散り去ったことはかえすがえすも残念なことである。戦後は男女とも進学や都会に職を求める者が続出し、豊かな農村も後継者を失い、反対に都会人が平和な好還境の住居を求めて年々移住して来た。そのため、かつての純農村の姿は次第に失われ、その行方は推測すら出来ない現状である。
四、葬祭
村人の手伝い 昔から家々の交際の中で最も重視したのは「死儀普請」と称する二つの事柄であった。不幸にして死人が出ると、まず近隣の家々から部落全部に伝達された。知らせを受けた家では仕事を打ち切り、すぐ死人の家にはせ寄った。おくやみもそこそこに、男衆は手わけしてお寺方回り、親類方回り、棺や仏具の手配、料理材料の買い物、火葬場の清掃整備など、女衆は家の片づけ、掃除、炊き出しなど、みなが日頃の小事を忘れてわがことのように飛び回って手伝いに励んだ。普請の手伝いと同様、「遠い親戚より両隣」のことわざのとおり、単なる形式的なことでなく、真実の助け合いがかわされていた。この温情あふれる交流は、本村のような苦楽をともにする純農村に芽生えた美風であり、その単位共同体が部落であるといえよう。戦時中の困苦欠乏時代はもちろん、戦後すべての物心が移り変わる世相に至っても、事あるごとにその温存を見ることが出来る。
夜とぎ(お通夜) 死人は「出居」にヒザを折り立てて(土箱に納めるため)寝かせ、必ず北枕、西向きにする。(これは釈尊涅槃=ねはん=にちなんだ形)両手は胸で合掌させ、数珠をかけ、顔には白紙、体には布の白衣をかけ枕元には「三つ具足」「お鈴」を飾る。供華は青葉の「まき木」を仏壇と枕元に立てる。また、遺体の白衣の上には「刃物」(刀剣など)をのせて置く。これは遺体の魔よけのまじないである。急報でいち早く近くの寺から坊さんがかけつけ、「枕経」をあげる。夕暮れになると手伝いの男衆や親類の人も集まって来て、女衆の作った手料理と「おむすび」(おにぎり)で夕食をとった。「親の泣き寄り他人の食い寄り」は明治の中頃までのことであって、今は泣き顔やしおれ顔を眺めると、かえって食欲も減退するであろう。
夜になると「上とぎ」の人々が集まって来る。お坊さんのお調子で一同が「正信偈」をあげる。次に枕元の仏に阿弥陀経が一巻あげられ、坊さんのお説教がある場合もあり、人々は互いに故人の思い出やくやみなどをして帰る。あとに近親の者だけが残ると一層かなしくなる。夜も更けてくると「ゆいがん」(よおが、またはゆいがともいう)が始まる。まわりにびょうぶを張りめぐらせた中で、まずかみそりで故人の髪をそり、体をふき清め、薄い寒冷紗のような布切れ(針で縫わないもの)を着せ、数珠をかけて合掌させて「土箱」(土葬時代の名称であろう、板で作った四角い箱で外側は紙ばり)の中に納める。なわかけの前に近親者に最後の顔、姿を見せる。とくにかわいい子供や、若い夫を失った遺族の場合は、その悲しみの声が夜のしじまに響き入り、この世のあわれをさらに誘うようであった。最後の対面が終わると、土箱には縦横にわらなわがかけられ、棺に納められる。この「ゆいがん」をする者は町方では傭人に依頼するが、農村では村内の経験者か親類の者が二、三人で当たる。棺は昭和になって共同棺が設置されるまで、個々に棺屋で白木造りの新しいのを作ってもらった。大人用、子供用、彫刻飾りはその分に応じてさまざまであった。形は昔の殿様が乗ったおかご型、鳳凰の屋根の鳳輦型、二重、三重の塔型があった。これらの美しい棺はともに火葬場で焼くのだが、次第に不経済と考えられ、昭和の初め頃に村一円の共同棺が設置され、戦前戦後と長く使用した。仏壇のようにきらびやかで優雅なもので、大人用、小人用もあり、ゴムタイヤの車輪付の非常に便利なものであった。戦後四十年頃から次第に町の葬儀社の霊枢事を使うようになったため、共同棺とともに各部落の火葬場も次第に使用しないようになった。
葬式 通夜の翌日はたいてい葬式となるが、その日が「友引」であったり、近親の者が遠方にいて帰りを待つ場合は、さらに一日延期した。
午前中は村の手伝い衆が棺、お供物、中陰料理、火葬認可などの準備をし、午後の定刻までに親類、友人、村人など多くの人々が参列する。七条袈裟姿のお手継ぎ寺の住職が導師となり、まず内仏の続経を終え、お棺の前で野送りの式が始まる。元来は野辺であげられた式だろうが、今は屋内で行うので、導師はくつ、その他の僧侶はぞうりをはいて、必ず立ち並ぶのである。最初に伴僧(お鈴たたき)がお鈴を打ち鳴らし、葬式独特の哀調を込めたお念仏を唱え、導師の焼香、弔辞、弔電が読まれ、導師のお調子で「正信偈」があげられる。しばらくして氏名を呼びあげて、喪主以下家族、近親、その他の順にお焼香が行われる。勤めが終わって僧侶が退場すると、参詣人も家の前に並ぶ。お棺をかつぐ者は喪主以外の故人の卑属男子で、布の白衣を着てぞうりばきである。家の前で高々といったん差し上げてから、お棺はしずしずと野辺の火葬場に向かい、その後に親属一同や村人の列が続く。
棺が家を出るに先立ち、お供えの盛りかごが玄関先で待ちかまえていた子供達に配られる。昔の子供達はおやつが十分与えられていなかったためか、ワーッとわれ先に、受けとるというより奪い取るような感じだった。「葬式の盛りもんわけるような」という例えも今は見られないし、想像もされない。仏式(浄土真宗)葬儀の式次第は昔も今も変わらないようだが、昔は時折り焼香順位についての争いなどがあったようである。昭和になると飾り付けやお供え物も次第に華やかになった。昭和十一年に生活改善が叫ばれ、次のような自粛が要望されたが、終戦後、生活水準が高まるにつれてすべてが豪華に流れ、部落民の手伝いによっていたものも万事請け負い式の町の葬儀社に委託し、霊枢車で金沢、松任市営火葬場に運ばれるようになった。
葬儀の改善 葬儀は哀悼の誠意を表わし、厳粛鄭重に執行すること。
一、葬儀準備
イ、葬儀執行に際しては、喪主は挙式方法につき社会教育委員、区長に諮り改善の徹底を期すること。
二、挙式
イ、告別式および葬儀執行の時刻はこれを厳守すること。
ロ、霊前の供え物は質素を旨とし、放鳥、造花、花環などは廃すること。
ハ、焼香は親近者および代表者のみ行うこと。
ニ、手伝い人は近親者または隣組の者に限ること。
ホ、適当な時を選び会葬者に対し、僧侶は法話をなすこと。
三、饗応
イ、葬儀前後の食事を供せざること。ただし遠方の客、親近者はこの限りにあらず。
ロ、葬儀当日は絶対酒を出さねこと。
ハ、通夜は饗応せねこと。
ニ、菓子やこれに類する物を配与しないこと。
四、儀礼
イ、香典は五十銭以内とすること。ただし特別縁故の者は一円以内とする。
ロ、香典返しおよび忌明けの配物並びに饗応はこれを廃し、回礼またはあいさつ状にとどむること。
ハ、通夜はなるべく親近者に限ること。
五、服装、葬具
イ、なるべく産業組合または部落において共同喪服を備え、これを使用すること。
ロ、産業組合または部落をもって共同棺を設置すること。
六、その他
イ、葬儀改善により節約し得たる額の幾分はこれを社会公益事業に寄贈すること。
火葬 火葬場はほとんど各部落ごとに隣部落との地境に造られていた。昔は野辺に露天掘りの四角い穴を掘り、回りは石積みであった。その穴の真ん中へ故人が北枕、西向きになるように土箱を入れた。今でも人間が死ぬことを「御西(ごさい)向く」というのは「仏説阿弥陀経」の中に「従是西方過十万億仏土有世界名曰極楽」と記されているからで、極楽の方を向く意味である。
土箱の下や回りにたきぎを詰め込み、上には野炭と祢する下等の木炭一俵をのせ、さらにわらで覆う。昔のわらべ歌に「おばァばどこへいく、しいろいあかば(美しい着物)きて、すみいっぴょかずいて……」とうたわれたとおり死ははかないものである。赤く両眼を泣きはらした遺族は、最後の涙をしぼりながらわらに火を付けて合掌して帰り、白衣を着た者はぬぎ、ぞうりは捨てて帰る。
この火葬は経験と熟練が必要であった。各部落の熟練者が頼まれてその世話をした。明朝までに完全に焼くために夜中に一度調べに行く必要があった。よほど勇気のある者でなければならなかった。この火葬場も雨天や降雪の場合に火葬が至難なため、明治末から大正初めにかけて、かわらぶきの建物が造られ、その中にかまどを設けるようになった。戦後四十年頃からは霊枢車で金沢市や松任市の火葬場で、短時間で火葬し、遺骨を持ち帰ることが出来るようになった。
中陰 野送りをして帰るとすぐ、近くのお寺の坊さんにより中陰の読経が始まり、一同がお参りする。この時、仏壇のお花は「中陰花」といって、花屋で立てた紅色系の花でなく、地味な白黄色のものを供える。読経が終わると「朱家具」と称する一切が赤塗りのぜんとわんに精進料理が並べられ、遠方の者から先に座についていただく。この料理は昔は手前料理だったが(村の手伝いの女衆がつくる。材料は町から買う)、戦後は専門の料理人の仕出しになった。また、この料理でご飯を食べるのを「おぶくをいただく」とか「おときにつく」といった。昔はこの「おぶく」をいただいている間は火葬の最中であったが、霊枢車で野送りする現在は「骨上げ」後の中陰になってしまった。
骨上げ(骨拾い) 中陰が終わると、近親の者以外は帰宅する。翌朝はこの近親者一同が火葬場に行って、変わり果てた白骨を拾い上げる。長い青竹を割って作ったはしで、皆が少しずつ灰をかきわけてお骨を拾い上げ、素焼きの骨がめに納めて家に持ち帰り、「骨堂」と称する白木で造ったお堂に納め、「出居」の床の上にすえ、「三つ具足」お花を供え、「金蓮」「銀蓮」を並べる。お寺の坊さんが来てお内仏やお骨堂にお経をあげ、そのあとにあの有名な蓮如上人の御消息「夫レ人間ノ浮生ナル相ヲツラツラ観ズルニ…………朝ニハ紅顔アリテ夕ニハ白骨トナレル身ナリ」の御文様を拝すると、「サレバ人間ノハカナキ事ハ老少不定ノサカヒナレバ」とだれもがありがたい教趣に感銘するのであった。
追善法要 葬式後も毎日お坊さんが来て枕経から一週間続けられる。また、なくなった人が女であれば三十五日間男であったら四十九日間、家族の者や他家に嫁いだ故人の娘まで「精進」をする。肉食を常にしていなかった昔は厳格に実行されたが、段々魚や肉類を多く常食するようになり、とくに発育盛りの青少年の栄養を考慮するようになった現在では「精進は心ですれば」など、つごうの良い理由を並べてその期間が段々短縮されている。
元来、「精進」は語句のとおり内面的なものであったが、その手段として行動化して形式的になった。今日のような複雑な生活形態では、心はあっても行がともないがたいのが実情であろう。期間が終わると「精進あげ」の法要が営まれる。お坊さんの読経後、集まった近い親類ともども「おぶく」をいただく。家に据えられてあったお骨はお墓に納められ、「お舎利さま」と称するノドのお骨は後日、京都本願寺の納骨堂に納められた。最後に残ったごく近親者には「しょうばき」と称し、故人が生前持っていた品物を分配するのもこの時であった。即ち、故人の遺品をいただいて、それによって故人の恩恵を常に忘れず、謝しながら、これに報いるためにより良く精進する意味であった。さらにお寺に対しては「志納経」「永代経」といって、分に応じた志を納め、故人の「法名」が集録され、その菩提が弔われる。寺院内に今も掲げられた多数の法名札がそれである。精進あげ以後は毎月の命日を「精進日」とし、その前日を「お逮夜日」といってお寺方から忘れず来てお経があげられる。遺族は故人をしのび、遺徳に謝して「おばく」や新しいお花を供え、仏壇に法名を掲げる行事を忘れず厳守した。昔はそのようにねんごろな家を「信仰心の厚い感心な家」と風評され、世間の信用や婚姻関係にまで影響したものであった。また、年忌法要(法事)も忘れずに営まれた。一周忌、三年、七年、十三年、十七年、二十五年、三十三年、最後が五十回忌で、この法要は「五十年間も追善法要を勤めたのはめでたい」という趣旨で、朱ローソク、松花。「なまぐさおぼく」と称し精進料理でなかった。
このように故人に対しねんごろな追善法要が重ねられるのであった。打算的な者の言葉に「死んだもんな三年間ものを食う」とまでいわれるほど大変なことであった。このように日常の村の生活を考えると、確かに先祖の加護のお陰が子孫の生活を維持し、繁栄させたと思われる。どんな理屈より、祖先の築き上げた家名や信用と財力が自分の生活の基盤であったのは事実であった。そしてこれに報謝の志がある者は累進し、忘却するような者は衰退した、と述懐する古老の話はあながち偏見ではないと思われる。
[part3] part4へ >>