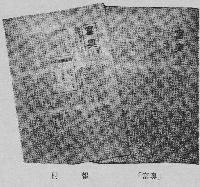<< part2へ [part3]
==第三節 公民館の事業==
第三節 公民館の事業
公民館では社会教育の本質から見て、社会教育を振興する道は住民の自己教育の意慾を高めるにある。それには団体組織を通じて行われなければならない。それが自主的に横極的に行われる事が大切である。わが公民館はとくに昭和二十六年以来前述のような考えに基づいて、わが村の教育体系の確立を図ることに力を入れ、すべての村人を教育的に組織化して、ゆりかごから墓場に至るまで教育に親しむ機会を与えて、明るい住みやすい楽しい生活の出来る社会を作るということにねらいをおいてきた。
そのために社会教育団体の結成と育成に力こぶを入れ、昭和二十年十二月十三日に戦後の廃墟の中に結成された青年団と国防婦人会から母の学校に、母の学校からさらに民主的に転身してきた地域婦人会を結成、今一つは郷土開発と産業振興を目ざして昭和二十五年に結ばれた青年産業研究会があった。
昭和二十六年以降社会教育団体の結成と育成に力を注ぐようになってから創設されたものは、幼児教育の振興をめざして昭和二十六年九月一日に初めて開設した季節保育所がある。それは学校へ入るまでの子供のしつけに重点をおいて運営してきた。次に小、中学校の学校教育を終えてから成人式までの働く青年を対象としての青年学級が、昭和二十六年六月に青年の学習意慾によって生まれた。さらに青年団運動を終わった二十六歳以上、三十歳までの青年団OBによる産業教育活動と自己研修を主眼とした青年産業研究会が二十六年十一月二十三日の動労感謝の日を期して青壮年自からの手で発足したのである。また、年と月を同じくして、村民体位の向上と村の体育文化の振興を図り、健全娯楽によって明朗な村を造ろうと十一月三日に体育協会が誕生した。越えて昭和二十九年十一月十一日には三十一歳以上四十五歳までの壮年が、われらも壮年の力を結集して何か一つ郷土の発展に貢献しようではないかと発奮、青壮年連盟が勇躍して出発。その翌々年の昭和三十一年一月十八日には年齢四十六歳以上の人達が青年や壮年に劣らない元気をもって自己研修と郷土開発に協力しようと健寿会の名称のもとに結集した。
こうしてそれぞれの団体が自主的に積極的に、その団体の本来の使命と責務を果たすべく、適応した事業を活発に行うようになって、村の中は非常に明るく、青年といわず壮年といわず、婦人といわず、老人といわず、みんなが住む郷土を立派に栄えさせよう、みんなが仲よく幸福な生活をしようという共同の目標に向かって手を握り合い、村には一貫した生命が流れてきた。
こうして社会教育を進める公民館運動のその事業が完成してきた。
昭和三十二年一月二十一日、運営審議会によりこれら社会教育団体がそれぞれ個々の団体の存立意義を解し、結成の精神にのっとり、健全な発育を遂げることが出来るように、精神的、財政的に団体育成に努めてほしいとの切実なる声により、次のように方向が定められた。
野々市町富奥公民館 運営及び活動方針
1、運営方針
(イ)公民館の施設設備の拡充を図り、施設公民館として地域住民の集いの場、学びの場、憩いの場としての使命と機能を充分に発揮し、公民館設置の趣旨と精神にこたへ、地域住民の期待にそわんことを期する。
(ロ)社会教育関係団体と連携を緊密に保ち、その育成助長に重点をおき、各団体の団体人格を尊重し、その特性を生かし、各団体をして自主的に積極的に団体本来の使命と責務を遂行でき得るように助言、援助をなし、しかして全住民教育の完壁を図る。
(ハ)地域的、組織的活動の主体たる分館活動を促進し、その振興と充実を図り、もって公民館運動の普及徹底に万全を致す。
2、活動方針 (略)
3、社会教育団体育成方針(略)
一、館報「富奥」発刊
公民館と各家庭の連絡を緊密にするために昭和二十四年十一月一日、時の館長宮岸清さんをはじめ竹内主事を中心に、運営委員の皆さんによって館報「富奥」が出版された。これに先立って富奥村では昭和九年、時の村長小林千太郎の時代から富奥村自治会が発足し、会長は村長が兼務して村報「富奥」が発行されていた。これには役場のこと、産業組合のこと、農会のこと、消防組のこと、青年団のこと、女子青年団のこと、青年学校のこと、婦人会のこと、国防婦人会のこと、小学校(尋常高等)のこと、軍人分会のことなど村勢全般のことがらがくわしく記載され、毎月五日発行され、全戸に配られた。村民はこれによって「村」に対する関心を高め、村人の修養を向上させる上に貢献した。しかし、大東亜戦争が終局に至るにつれ、発刊物の規制をうけ、それがいつとなくとぎれた。
次に村報「富奥」の第三巻第二号の昭和十一年二月五日に発行された一文を記して後世に残したい。
故宮森久親君を悼み併せて所感を述ぶ
村長 小林千太郎
宮森君は昭和二年本村に職(小学校の先生)を執らるるや、九年間一日の如く教育のため、その他各種方面に盡瘁され、本村発展上多大なる実蹟を挙げられ、村民一同前途を大いに嘱望していましたところ、去る十二月(昭和十年)三十一日、三十二歳なる活動の好時期に念仏の息絶えられた。噫、独り君一家の不幸のみにとどまらず、我富奥村のため、実に悲しみの極みである。
君は温厚篤実の性格を備え、しかも意思強固にして、思い立った事は徹頭徹尾やり通さなければおかんという風で、それがため事にあたり、寝食も忘れるほど熱中された事は、良く世人の知るところである。
殊に君は常に仏教信念を根底とする生活をなされ、本誌(十月号)に四馬の聖訓を挙げて、自己の信念のほどを披歴なされ、又私に対し「村長様、この人生は苦悩の世界である故、念仏で日暮ししまいかね」と申された事もある。その後日浅くして病魔に冒され、病勢にわかにつのり、遂に本国に還られました。これ真に還相廻向の人なりと信じます。私は「負うた子に教えられて浅瀬を渡る」の諺の如く、君によって層一層人生無常を悟らしていただいたのである。君の生前を追憶するとともに、私自身の信ずるところも皆様の前に申しのべて見たいと思う。
現実の社会は何といっても悩みの世界である。悩みの世界は無明である。無明の世界は光明がない。光明がないから歓喜もなくすべてが不純である。
「鳴呼吾等が無明淵源の病は、念仏腑臓の霊薬にあらずんば、治するに由無し」とは法然上人二十七年間、限りなく内に求められた痛ましき体験である。(中略)
夫婦という因縁和合して一家は繁栄するが如く、社会もまたすべてが因となり縁となって組織せられる。それ故に一方を倒せば、又一方も倒れねばならない。ここにおいて共存共栄の原理が認められる。共存共栄の精神は自利利他の行である。この行は菩薩の道である。自利利他円満は仏心の表現であって、念仏は正に大悲の顕現であるからして、われらの生活はこの念仏によって歩一歩と光明土に向っての歩みである。この生活こそ仏陀及び宮森君の私に教えられた一言が真実の道であると私は信ずる。
このように歴史の深い村報「富奥」を館報「富奥」として、郷土を愛し、郷土を築き上げようと懸命の努力を集注し、継続されたのである、当初は戦後のことでもあり、紙や予算の関係から隔月発行で年に六回、その後公民館に広報委員会を作り、広報活動に主力を注ぎ、その功を奏したのも全くその基をなすものは村報「富奥」である。
二、季節保育所開設
わが公民館では終戦後初めて、昭和二十六年九月一日から一ヵ月の予定で幼児の福祉増進と農繁期の労力調整を目的として、季節保育所を開設した。
保育所を開設することとして希望申込みをとったところ、百四十余名の多きにのぼった。このため公民館ではわが村の地理的関係から見て、小中学校の一部を開放して第一保育所とし、いま一ヵ所は下林の定林寺を住職増山了栄氏の自発的な協力を得て、第二保育所として発足した。保母としてはお寺さんの奥さん達の積極的協力を得て、香城すみ子、白山富子、香城清子の三人を第一保育所、増山歌子、加藤典子の二人を第二保育所勤務として、第一保育所は児童数九十人、第二保育所は四十人を収容して保育に万全を期した。幸いにして一人のケガ人もなく三十日にわたる保育を無事終わった。
この第一回目が終わった十月一日に、反省会を公民館で保母と公民館厚生部の人々と合同で開いたところ、児童のお母さん方や家庭の方々から「今年は公民館で保育所を開いてもらって、子どもに手をとられなくて、大だすかりであった」と喜ばれた。また、「来年からもこれを農家の忙しい春、夏、秋の三期にわけてやってほしい」との希望が非常に多く、公民館としても「村人からそんなに喜ばれているなら開設した意義がある」と意を強くし、副館長である田中忠信助役と定林寺の増山了栄さん夫妻の協力を得て、引き続き季節保育所を開くこととなった。季節保育所は村人から非常に喜ばれ、公民館についての関心が高まり、ぜひ必要な存在となった。
この季節保育所は昭和二十六年の秋に始めてから昭和三十二年三月三十一日まで六年の長い間、公民館の手によって運営されたのである。昭和三十二年度からは野々市町の第二保育所として町営となり、年中常時開設することに変わった。そこで当公民館では昭和三十二年三月三十一日午後二時から公民館で、その閉所式を母の会員と保母の先生方とともに盛大に行った。その席上、保母として五年間勤続した香城はま子、香城清子、三ヵ年勤続した西村みのる、一年勤務の山口花子の四人を、その間の功績大なりとして感謝状に記念品を添えて公民館から贈った。
この六年間に保育所のために尽くされた人々は、時の村長や田中忠信助役、公民館主事の橋田章、保母としては白山富子、香城すみ子、増山歌子、加藤典子、香城はま子、香城清子、西村みのる、山口花子の八人の先生がある。この外に民生委員であった増山了栄氏がよく協力した。
この保育事業はもちろん社会福祉事業であって、公民館の分野に属する事業ではなかったのであるが、昭和二十六年当時、わが村では保育事業が取り残されており、中島喜寿館長が幼児教育の振興という意味で季節保育所を取り上げ、これによって村人から公民館の重要性が改めて認識された。
[part3] part4へ >>